ライバル著者に勝つ!「類書との差別化」
2014/02/06優秀で高い地位の人ほど"不利"な事とは?
こんにちは、樺木宏です。
仕事もある程度上の立場になると、アドバイスを受ける機会が激減します。
上に行けばいくほど、その傾向は顕著。
「社長、あなたのビジネス、ライバルと置き換え可能ですね。差別化されていませんね」
などと言ってくれる社員はいません(笑)
平時にはこれで良いのですが、これが商業出版になると、話は変わってきます。
というのも、すでに本を出している優秀なライバル著者が大勢いるから。
いくら有益で素晴らしいノウハウでも、同じ内容で先に本が出ていれば、
読者はもう「お腹いっぱい」の状態でしょう。
また、今世の中に何が求められているか、という時代性もあります。
20代のゆとり世代向けに根性論でがむしゃらに働こう、というメッセージを送っても、
響く可能性は低いですね。
このような事情があるので、商業出版では「自分を客観視」することがとても大切です。
・自分のノウハウは、ライバルと比べて、読者にどのような新しいメリットがあるか?
・今の時代、多くの読者が悩んでいることと、自分のノウハウはどう繋がるのか?
こうした客観的な視点がとても大切。
そしてそれが自分では難しい、と言う事であれば、第3者のアドバイスが有益なのですね。
あなたのまわりにはそうした人がいますか?
優秀な人で、立場が上であればあるほど、ここは盲点になりがち。
自己チェックしてみて下さいね。
2013/12/25本を書きたいと思ったら気をつけたい、たった1つのこと
こんにちは、樺木宏です。
「自分は○○が得意だから、その本を書きたい」
「自分のビジネスの専門分野で、本を書きたい」
という人は多いですね。
でも、ちょっと待って下さい!
そこには落とし穴があるのです。
どんな落とし穴かといえば、世の中には「似たような本がいっぱいある」という事。
いくら素晴らしい内容で、あなたの実績が輝かしいものでも、
同じような本が先にでていたら、売れません。
売れないということは、企画が通らないということ。
だから、自分の書きたい本が、すでに世の中にでていないか、調べる必要があるのですね。
そして、「同じような本が何冊もあった!」となっても、気落ちする必要はありません。
むしろ、ある程度は歓迎すべきこと。
なぜなら、その本を読みたいという人が、世の中にはいっぱいいる、という事だからですね。
もちろん、出尽くしてしまって、そのジャンルは枯れてしまっている、ということでしたら話は別ですが・・・
そうした場合は、柔軟に、方向性を変更していきましょう。
今日お伝えしたのはちょっとした知識ですが、商業出版では、採用確度が何十倍も変わってくるコツ。
ご参考になればと思います。
2013/11/12あなたの企画を"差別化"しよう
こんにちは、樺木宏です。
さて、出版企画の最大のハードルはずばり、類書との差別化です。
"読者に、今までの本にはない、新しいメリットを提供すること"
これが差別化です。
これが出来れば、いくらでも本が出せるといっても過言ではありません。
え、ほんと?と思われるかも知れませんが、本当です。
企画が通るのに必要な要素は他にもありますが、
それはさほど高いハードルにはならないことが多いからです。
例えば、読者ニーズ、という要素。
どういう本が売れるテーマか、というのは、過去の売れ行きを調べれば分かること。
そのテーマから選べば良いだけの話です。
あるいは、著者の書く資格、という要素。
この著者は書くのに相応しい人か?という編集者のツッコミにも、
ある程度ビジネスをしてきた人なら、プロフィールを作り込むことで対応できます。
これも、すでにノウハウがありますから、活用すれば良いだけ。
でも、類書との差別化は、難しいです。
売れている本は変わっていきますし、あなたの強みが何かで、
正解はまるで変わってしまうからです。
だから、単純にこうやれば良い、という結論を書けばよい、というものではありません。
それは抽象的で、具体性に欠けるものになってしまいます。
また、本を何冊も出しているからといって、差別化のノウハウがあるとも限らない。
それはたまたまその著者が優秀で、差別化されたポジションをとれただけの場合も多く、
他の人で再現できるかは別の問題なのです。
そこで必要なのは、著者の強みを、差別化に結びつけるノウハウ。
例えば私であれば、下記のような差別化ポイントを企画に活かした事例があります。
https://pressconsulting.jp/books/
2013年9月の事例から下に見て行くと、
"職員室の無い、いじめの無い小学校の"先生
"日本で初めて、小さな士業事務所のアライアンス戦略を提唱する"税理士
"破綻寸前の会社の救うことに特化した"経営コンサルタント
"筆跡を鑑定するだけでなく、公認会計士でもある"コンサルタント
いかがでしょうか?
差別化された著者のポジションをつくり、出版に活かす感じを、
イメージしていただければ嬉しいです。
その感覚を自分の企画にも活かし、ぜひ"類書との差別化"をしてみて下さい。
きっと、本を出し続けることが出来るようになりますよ。
2013/08/05マンガ風の表紙にすると売れる、は本当か?
こんにちは、樺木宏です。
とある業界紙を読んでいたら、
「15~44歳までの男女75%はマンガ好き」
というアンケート調査が出ていました。
大人から子供まで読むのがマンガですから、情報発信をマンガに絡めるのは理にかなったことですね。
例えビジネス書でも、「マンガ=付加価値」となるわけです。
ビジネスパーソンの皆さんの、情報発信の手段としてマンガにする、
あるいは既存のマンガになぞらえる、と言う事は選択肢としてアリなのです。
ただ、ここで1つ注意点があります。
安易にマンガにすれば良い、という事ではありません。
そこを見落とすと、逆に評価を下げてしまう可能性もあり得ます。
例えば、必然性は必須です。ミリオンセラーになった「もしドラ」では、10代の女の子でも読める経営書、
というコンセプトがありましたから、「分かりやすく伝えなければいけない」という必然性があり、表紙や挿し絵がマンガになりました。
ただ安易に萌え系の表紙にしただけでは無いのですね。
マンガ風やライトノベルなど、取っ付き易さは皆さんの付加価値になり得ますが、
それ以前に大切なのはコンセプト。
ここをぜひ押さえて下さい。
2013/07/30あなたの企画が「どこかで読んだことのある本」にならない為に
こんにちは、樺木宏です。
書店には本が沢山並んでいますね。
実にその数は8万点弱もあり、つい最近まで点数は増え続けていました。
ということは、皆さんの企画は、差別化しなければいけない、という事。
なぜなら、いかに有意義な企画であっても、同じような内容の本がすでにあったら、
後から出す意味は無いからです。
ここで、ひとつのノウハウをお伝えしたいと思います。
それは、
「差別化とは、読者の目線で考える」
ということ。
類書との差別化と言っても、類書との違いをピックアップするだけでは不十分。
それが読者にとってどういうメリットがあるのか?が無ければ無意味です。
逆に読者にとって意義ある類書との違いであれば、その本は魅力的=売れる可能性が高まる、
という事になります。
でもこの考え方、客観的には分かっいても、いざ自分の企画を考える段になると、
意外と難しいもの。
優秀な著者の人でも、ちょっと意識が外れるだけで、ついやってしまいがちなのです。
ここは十分に注意して「差別化とは、読者の目線から言う」ことを意識して行きましょう。
そうすれば、あなたの企画は確実に差別化され、かつ魅力的になります。



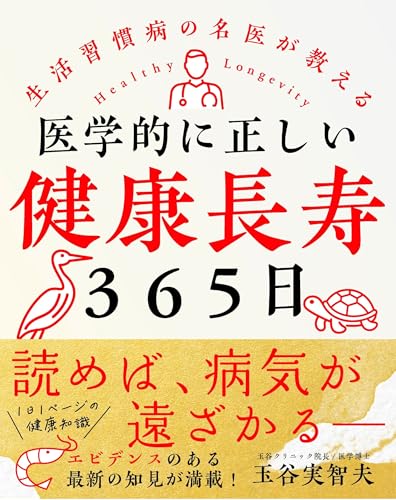
 読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
