いなければ始まらない「読者ターゲット」
2017/11/30出版企画は"考えはじめ"が9割
こんにちは、樺木宏です。
「本を出そう!」と思ったら、次にやるのは、
「何を書くか」を考えることですね。
大多数の人はまず、「自分の書きたいこと」を考えるでしょう。
自分の経験、実績、ノウハウ・・・といったものから、
「こういう本が書ける」という風に、考えていくことと思います。
実はここに、もう落とし穴があります。
そういう順番で考えること自体が、すでに出版から遠ざかってしまう危険があるのです。
なぜなら「読者ではなく、自分が満足する本」を考えてしまうから。
「こんな風にかけたらカッコいいな」とか、「ライバルをあっと言わせる内容にしよう」
と考えていくと、どんどん「自分やライバル」が満足する本になっていきます。
それに対して、読者はもっと初歩的であったり、分かりやすかったり、誤解を解いて欲しいと思っていますから、
どんどん読者から遠ざかってしまうのですね。
これがやっかいなのは、本人は一生懸命考えていること。
ただ一生懸命考えれば考えるほど、「自分の書きたいこと」に熱中してしまい、
「プロ向けの専門書」になっていってしまう。
それでは残念ながら読者がとても少なくなってしまいますし、
「こんなに頑張ったのに、企画が通らなかった」ということで、
心が折れてしまいがちでもあります。
こうならないためには、自分が書きたいことはそこそこに、
「読者はどんなことに悩んでいるのか?」
「それはどの程度のレベル感なのか?」
にアンテナを張ること。そしてそれを見続けることです。
そうすれば、自分が書けることは潜在意識が分かっていますから、
「これを書こう!」というアイデアは勝手に浮かんできます。
言い換えるなら、いったん自分のことは忘れて、相手の事を考える。
アイデアは、勝手に浮かんでくるのを待つ。
ちょっとした発想の転換ですが、効果は絶大。
ぜひ試して見て下さい。
2017/08/10一瞬で"読者目線"になれるコツ
こんにちは、樺木宏です。
商業出版のノウハウはいろいろ聞けども、いざ出版企画に反映するとなると、なかなか大変ですね。
例えばよくあるのが、「想定読者」を考える難しさ。
頭では、
「より多くの人に、より刺さるように」
「1人の読者をイメージする」
「素人レベルの人を想定する」
そうすれば、売れる出版企画になり、企画が通りやすい、というようなことは知っていても、
つくった企画がそうなっていないこともしばしば。
最初は無理のないことですが、出きるだけ短期間でこうした状態を抜け出し、
「読者が大勢いて、しかも刺さる」出版企画を、どんどん考案できる著者になりたいものですね。
では、具体的にどうするか?
先の想定読者の話で言えば、原因は「リアリティ」の低さにあります。
自分の企画を考えるとき、真っ先に思い浮かべ、かつ読まれることを意識するのは、
周囲の「自分に近い知識レベルの人」です。
そこに強いリアリティを感じてしまうと、どうしてもそこに引っ張られてしまうでしょう。
企画も自然とプロかそれに準じる人向けの内容となり、妙に専門的で、読者が狭められたものに
なってしまうのです。
そうならない為には、頭でノウハウを覚えるのではなく、
「今まで感じていた臨場感を利用する」
ことがおすすめです。
例えば、TV番組。
知っている人も多いと思いますが、バラエティ番組の対象は、各社とも、
「小学校5年生」
を想定してつくっているそうです。
だから誰でも気軽に見れるし、分かりやすいのですね。
それは商業出版の本でも同じです。
だからあなたが書きたいテーマで、バラエティ番組などをやっていたら、
それはあなたの出版企画の最高のヒント。
「なるほど、こうやって表現すると素人さんは分かりやすいのか」
「ここでわざとゲストが質問をして、読者が分かりにくそうなところを補足しているな」
という気づきを、無料で教えてくれるのですから、見ない手はありませんね。
商業出版の著者としてのヒントは、いろんなところにあります。
バラエティのTV番組なども、日頃はあまり見ないかも知れませんが、
こうした目線でぜひ見直してみて下さいね。
2017/02/08"決定権"は読者にある、と知るだけで上手くいく
こんにちは、樺木宏です。
商業出版で本を出すことの難しさって、なんだろうな?とよく考えます。
著者はその道のベテランでありプロだし、読者は素人。
普通に考えれば、ためになる内容をいくらでも伝えてあげられそうなものです。
しかし、それが伝わらない。
なので売れない。
だから本を出版することは難しい、となってしまいがちです。
なぜそうなってしまうのか?
その原因の1つは、著者が「主導権」を勘違いしていることです。
著者はプロなので、「主導権」が自分のほうにあると思いがちなのですが、これは実は逆です。
読者の方が、主導権を握っているのです。
例えば、「タイトル」。
プロである著者が好むのは、「内容の説明」です。
著者がコーチであれば、「コーチ術」「コーチング」というストレートなタイトルをつけたくなります。
しかし素人である読者は、「それって自分にどう関係あるの?」という醒めた目で見ています。
だからタイトルでは、「読者にどう関係があるのか」の方が、内容そのものよりも大切。
そう考えると、ストレートに行くのではなく、
「読者にとってどんなメリットがあるか」
「それは普通の人にでも再現できるのか」
を、工夫してあげればよいのです。
具体的な例を挙げると、
読者に「いまどきの子のやる気に火をつける」というメリットを伝えてあげて、
コーチングではなく「メンタルトレーニング」のように見せ方を工夫することもできます。
そうして出来たのが、
「いまどきの子のやる気に火をつけるメンタルトレーニング」飯山晄朗著(秀和システム刊)
という本のタイトルです。
この本は現在、続刊含めて10万部を突破しています。
「主導権は読者にある」と考えることで、企画の成否が決まり、
本が売れるかどうかも大きく左右されるのですね。
ぜひプロであるあなたも「主導権はあちらにある」と考えてみてください。
そして、あなたの著者としてのブレークスルーの一助となれば、嬉しく思います。
2017/01/25お釈迦さまに学ぶ、「売れそうだ」と思われる人の共通点
こんにちは、樺木宏です。
さて、私は仕事柄、商業出版で本をこれから出そうとしている人や、すでに本を出している人とお話をする機会が多いです。
というか、編集者以外ではそういう人とばかり会っています。
多くの人に会う中で、
「この人の書く本は売れそうだな」とか「さすがに売れている人だな」
と思うこともしばしばです。
そこであなたにお伝えしたいのは、
「売れそうだな、と思われる人」の、ある共通点です。
どんな共通点だと思いますか?
それは、ズバリひとことで言うと、
「自分の目線ではなく、相手の目線で話をする人」です。
こういう人は、必ずといっていいほど出版できるし、本が売れます。
商業出版で言い換えるなら、
「プロとしての著者の目線ではなく、素人としての読者の目線で本を書ける人」
ということだからです。
そこで私が思いだすのが、仏教の開祖、お釈迦様。
悟りを開くという、ある意味究極に高度な内容を伝えるために、
お釈迦様は、とても分かりやすい伝え方を心がけた、と言われています。
その1つが「対機説法(たいきせっぽう)」と呼ばれるもの。
これは何かというと「相手の能力や個性に応じて、柔軟に工夫する伝え方」です。
お釈迦様は、相手の理解度や立場、欲求に応じて伝え方を柔軟に変え、
どんなに無学の人にでも分かりやすく伝えることが出来た、と言われています。
著者の場合でも、リテラシーが低めの人にも分かりやすい内容にしてあげれば、多くの読者に届きます。
その証拠に、どのテーマでもいちばん売れるのは入門書です。
逆に言えば、著者のプロとしての理解度や欲求レベルでそのまま伝えてしまっては、
相手に伝わらなかったり、売れなかったり、場合によっては誤解されてしまうことすらあるかも知れません。
また、お釈迦様は自分の教えを残したいという弟子に対し、
当時高等な言語とされていたサンスクリット語で書くことを禁じ、
民衆にも親しみやすい口語、パーリ語で残すよう指示したと言われています。
まさに読んでもらうための配慮ですね。
親しみのある言葉づかいで書かれていれば、その人の心により深く届きます。
本であれば、その感動が口コミやSNSなどで周囲に伝染し、さらに売れるということにもつながるでしょう。
だから、「プロとしての著者の目線ではなく、素人としての読者の目線で本を書ける人」
は、売れるのですね。
逆に言えば、著者としての権威を高めようと、高尚なテーマを選んでしまったり、
難しい表現や専門用語を多用することは、ある意味とても残念な行為、とも言えるでしょう。
考えてみれば、仏教の歴史も「分裂」の歴史ですが、
その原動力はいつも、教えが難解になりすぎ、多くの人に伝わりずらくなったことへの反動でした。
いかがでしょうか?
あなたの書く内容がどんなに高度でも、「究極の悟り」ほどではないなら、
必ず分かりやすく書くことができます。
そしてそれは、あなたの本が売れて、ブランド力を高めるための近道なのですね。
ご参考になれば幸いです。
2016/12/21"忘れられていた読者"に向けて書こう
こんにちは。商業出版コンサルタントの樺木宏です。
本というものは、いくら素晴らしい内容を書いても、読む人がいなければ成り立ちません。
だから、「誰に読んでもらうのか?」は、出版する上でとても重要なポイントです。
多くの本が先に世の中に出版されているのですから、
「なんとなくこういう人が読者」
というのでは、なかなか企画が通りません。
そこで考えたいのが、「意外なところに読者がいないか?」という視点です。
例えば、ペットの本は、獣医さんが書く実用書か、ねこ好きの方が書くエッセイやマンガが多いもの。
そのテーマで類書を見回してみると、女性の著者が書くものが非常に多い。
その内容も、とても情緒的でソフトな感じです。
どちらかというと、右脳型の女性著者が、女性向けに書いた本が多い、というのが分かってきます。
そこで、「意外なところに読者がいないか?」と考えてみました。
実用書以外では男性著者が少なく、男性向けのペットの本はあまり無いのですね。
かつてダイエット本も、女性向けのものしかありませんでした。
そこに「オヤジダイエット」がでた事で、一連の中高年男性向けのダイエット本が
ブレイクしたことは、記憶に新しいと思います。
そのように考えると、
「左脳型の男性でもペット本を読みたいのではないか?」
という意外な読者が見えてきます。
それが実は、私が書いた「幸せになりたければ ねこと暮らしなさい」という本の想定読者です。
もちろん、それ以外にも読んで頂けるよう写真を多用してオールカラーにするなどの工夫はしているのですが、
基本的な想定読者は男性です。
いかがでしょうか?
このように、「意外な読者」を考えてみることで、あなたの企画も、
突然ユニークなものに変わり、出版の実現がグッと近づくことでしょう。
ご参考になれば幸いです。



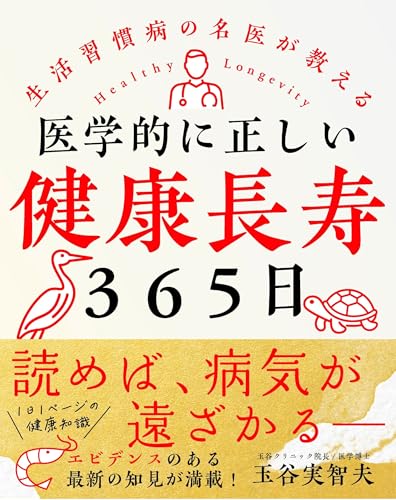
 読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
