いなければ始まらない「読者ターゲット」
2014/12/24何を書くかより、誰が読むかの方が大切です
こんにちは、樺木宏です。
さて、本を書くというと、
「何を、どう書こうか」について、考えますね。
あれも書きたい、これも書きたい・・・となるのが普通だと思います。
でも商業出版に限って言えば、
「誰が読むのか」を考えることの方が、ずっと大切です。
なぜかと言うと、
商業出版は、"読者に買ってもらわないと成り立たない"からです。
出版社の採用基準は、良い内容かどうかではなく、売れるかどうか。
だから、
「読者が書店で、タイトルに目を止めて、手に取ってくれるかどうか?」
「手に取って立ち読みしたときに、目次の冒頭で"自分の為の本だ"と思ってくれるかどうか?」
本を買ってもらう上で最重要なのは、そこなのです。
こうした事を知らないと、考える順番を間違えます。
まず自分が書きたい事を決めてから、誰に当てはまるかを考えてしまう。
そうすると、読み手からみると、「後付け感」を感じてしまったり、
「(自分の悩みは)そこじゃないんだよな・・・」となってしまいがちです。
逆に、最初に誰が読むかを考えて、その人に向けて内容を後から考える。
そうすると、「自分のための本だ」と深く刺さる人が、必ず出てくるのです。
売れかどうかは、こうした事で決まりますから、
当然企画が通るかどうかも、ここがポイントなのですね。
いかがでしょうか?
自分よりも先に相手の事を考える。
それだけで、あなたの企画は格段にレベルアップし、著者としてのポテンシャルが引き出されます。
たったこれだけの事なのに、やらないのは勿体ないですね。
ご参考になれば幸いです。
2014/10/22出版企画書でまずチェックされるのは、読者の数です
こんにちは、樺木宏です。
さて、今回の記事は具体的な出版ノウハウの話。
出版企画書で、まず最初にチェックされるのは、
「想定読者の数」です。
もしここが足りないと思われたら、いかに充実した素晴らしい内容が書かれていても、
その企画が採用される事はありません。
出版社は出版に必要な費用を全額支払い、リスクを負うからです。
売れない本を出してしまえば、赤字になります。
編集者個人としても、そういう本が続けば社内の評価にかかわります。
だから、想定読者が少ない→売れる可能性が低い本→その企画はスルー
となってしまうのですね。
だから企画のアイデアが浮かんでそれを書き留めたあと、あなたが最初にすべき事は、
「この本を、読みたい人はどれくらいいるか?」
を自問自答することなのです。
さらに具体的に言えば、自問自答には、2つのチェックポイントがあります。
1つは、この半年〜1年以内に、類書が多くでているかどうか。
もう1つは、読者が100万人程度いることが示せるか。
です。
このうちどちらかを満たしていれば、読みたい人が大勢いる企画、ということです。
前者のように、類書が多くでていれば、それは売れているからなので、需要があることは明白です。
ただ気をつけなければいけないのは、あまりにも多く出過ぎている場合と、
そうなってから時間が経ちすぎている場合。
それはもう飽和状態になっていますから、難しいと判断されてしまうでしょう。
後者の100万人読者がいるかどうかについては、データで示す必要があります。
業界内の統計や、関連するサービスを利用している人数などを、数字で見せられるかどうかです。
ただここで注意したいのは、単純な年齢、性別、職業などだけでは不十分、という事です。
もっと具体的な"悩み"で絞り込まないと、人数だけ多くても売れない、と判断されてしまうでしょう。
いかがでしょうか?
想定読者の数に注目すれば、あなたの企画は最初の関門を突破し、
採用確度は大きく向上します。
ぜひこのノウハウを活用して見て下さい。
2014/08/12編集者がスルーする企画と、食いついてくる企画の違いとは
こんにちは、樺木宏です。
さて、出版企画は、提案したときのリアクションにより、2種類にわかれます。
・編集者が食いついてくる企画
と、
・見向きもしないでスルーする企画
です。
当然前者の方がよいですよね。
でも残念ながら、後者の企画の方が世の中には多いようです。
それを裏付けるように、出版社の中には、
"送られてくる出版企画や原稿を、ゴミ箱に捨てる係"
なる人が決まっていたりします。
それくらい、スルーされてしまう企画は多いのです。
では、そうならない方法は?
実戦的なことを1つだけお伝えするとしたら、
「読者を徹底的に寄り添う」事をおすすめします。
そうする事で、あなたの普通の企画が「深く刺さる企画」に変わります。
読者の側からしてみれば、自分以外にも大勢の人に向けた本よりも、
自分の悩みにぴったりフィットしていて、"まるで自分の為にあるような本"が欲しいからです。
その為にも、読者の悩みに寄り添うことが大切。
例えば勉強をテーマにした本であれば、
「出来ない人の気持ち、葛藤、過去の挫折、諦めの気持ち、恥ずかしさ」
といった気持ちに寄り添うことで、読者に深く刺さる本になるでしょう。
もし編集者が想定する読者と同じ悩みをもっていたら?それは絶好の機会ですね。
逆に、ここをおろそかにして、「有意義な内容を書いてあるのだから、読んでくれれば分かる」
「やりさえすれば出来るようになる」
などと、上から目線で行ってしまうと、よほどの実績がある著者でない限り、その企画はスルーされてしまう可能性が高いです。
他にもいろいろと企画のノウハウはあるのですが、いずれも準備や情報の蓄積が必要。
そうなると結局実践できずに、「スルーされる企画」になってしまう可能性が高いです。
だからまずは「読者の悩みに寄り添い、深く刺さる企画」にして行きましょう。
必ず企画の採用確度が上がりますよ。
2014/04/04"業界のプロ同士"の勉強会"の落とし穴
こんにちは、樺木宏です。
皆さんは、自分の業界プロ同士で、勉強会などに参加しているでしょうか?
ノウハウの共有や人脈をつくる上で、有意義なものだと思います。
ただし。
"著者"という視点からみると、1点気をつけたいことがあるのです。
どういう事かと言うと、
「そこで語られるレベルが、あたり前になってしまう」
事です。
これは、著者を目指す人、あるいは出し続けたい人からみれば、とても大きな落とし穴になり得ます。
なぜなら、
「読者のニーズを見落とす」
ことがあるから。
例えば、先日とても実績とノウハウのある著者と話していた時に、
「えっ、そんな事を普通の読者は知らないの?」
というリアクションがありました。
普段レベルの高い専門知識を情報交換しているので、まさかそんな基本的なことが
分かっていない人が世の中に多い、ということが盲点になってしまっているのですね。
これは、まさに「読者ニーズの見落とし」です。
そしてこういう人がどういう企画をつくるかと言うと、
「同業者からみてもカッコいい企画」
をつくろうとします。
そうなると、一般の多くの素人読者には、全く刺さらない企画、になる可能性が高い。
そうなると企画は通りません。
これは是非避けたい落とし穴ですね。
売れている著者とは飛び抜けて優秀な人では無く、素人レベルまで目線を下げられる人。
市場のニーズに気づける人、という事です。
ご参考になれば幸いです。
2014/03/04企画の大前提となる"読者ニーズ"の考え方
こんにちは、樺木宏です。
さて、商業出版とは文字通り「本を売るビジネスとしての出版」です。
出版社に"売れる!"と思われれば企画が通りますし、売れないと思われれば通りません。
だから、「この本を欲しがる読者は大勢いる=読者ニーズがある」
ことを示すのが、出版企画書の大切な役割です。
出版社は本を出すのに約300万円ほど掛けますから、
売れると言う確信がないと、企画にGoは出さないのですね。
では具体的にどうすれば?と言う事なのですが、
1)同じテーマの本が「今」売れている
2)読者が多いことを、統計などのデータで示せる
上の2つのうちいずれかが必要です。
1)について言えば、今売れていると言う事は、読者ニーズがある、という事。
なので、同じテーマであれば「まだ売れるかも」と出版社は考えます。
ただし、同じ事は皆考えます。
ベストセラーがでたら、似たような本が何冊も書店に並ぶことは当たり前。
そうなると、いかに早く動くかが勝負で、結局常日頃から読者ニーズのリサーチは欠かせない、と言う事になります。
また、昔に売れた本、ではダメです。
すでに読者ニーズは満たされてしまっているからですね。
あくまで「今」でないと、意味がありません。
2)の「読者が多いことを、統計などのデータで示せる」について言えば、「数字」が大切です。
まだ先行するベストセラーはない場合、客観的な信用があるのが「潜在的な想定読者数」だからです。
それも、単なる「20代後半男性サラリーマン・課長職」といった属性だけではダメで、
「その人の抱える悩み」にまで踏み込んでいる必要があります。
本はWebや雑誌と比べても高額な情報代ですから、悩みを解決したいと思っていないと、買ってくれないものなのですね。
いかがでしょうか?
読者ニーズと言っても、いろいろな注意点がありますね。
ここが企画採用の大前提となる大事なところですので、
企画考案の際は、ぜひ参考にしてみて下さい。



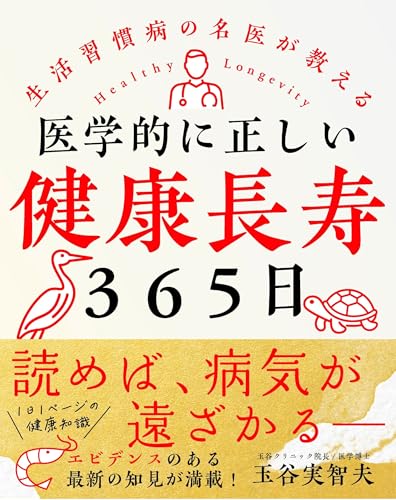
 読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
