いなければ始まらない「読者ターゲット」
2015/12/09読者層を広げ、読者数を増やす
こんにちは、樺木宏です。
さて、今回の記事でも、実践的な企画のブラッシュアップのアドバイスをお伝えしています。
たとえ本が出版されても、それがベストセラーとなっても、本を出し続けるためには、
結局は企画を考案し、ブラッシュアップすることはついて回るからですね。
そういう意味で、新人著者からベテラン著者まで、お役に立てるよう、意識してお伝えしていきます。
さて今回は、
「読者層を広げ、読者数を増やす」
ことをお伝えします。
このことをお伝えするのには、2つ理由があります。
1つは、多くの方が「読者数が少ない」企画を考案してしまうからなのですね。
あなたの今のクライアントや、身近かにいる人だけを対象にした本では、
読者数が少なく、手を挙げる出版社も限られてしまい、採用確度が低くなってしまいます。
そこで「もっと広げられないか?」と自分に問うてみることで、さらに売れる企画となり、
採用確度が増すでしょう。
2つ目の理由は、例え企画が通っても、部数が少ないとブランディング効果が低いためです。
そうなると集客効果や、講演依頼なども期待できず、次の出版の声がかかる可能性も低くなってしまいます。
そもそも商業出版する目的はそこにあると思いますので、本が出ても結果がなければ、本末転倒でsね。
でもいつまにか本を出す事自体が目的になってしまう人も多いので、こうしたチェックポイントはとても有効です。
このような理由から、もっと読者層を広げ、読者数を増やすことで、
ブランディング効果を高めていきたいですね。
例えば、下記の本。
「そのかめはめ波は違法です!──ワクワクドキドキ大冒険しながら法律武装」
http://goo.gl/vItq5o
この本は、弁護士が書いた法律の解説書なのですが、そう言うと違和感があるくらい、読者層が広がっていますね。
「法律に関心がない読者でも、読みたくなるような工夫」
が光ります。
法律に関心がある人だけに書いているのではなく、あえて「素人」に向けて書いていることが、
この本の素晴らしいところだと思います。
その事で、読者層を広げ、読者数を増やす事に成功しています。
いかがでしょうか?
上記は一例ですが、テーマや業界が違っても、あなたの企画でも活用できるノウハウです。
もともと関心が高い読者だではなく、もっと素人でも「自分事」と思えるような、
敷居の低いメリットを考案してみることで、多くの読者の心をつかむ事ができるでしょう。
ご参考になれば幸いです。
2015/11/18ブランディング効果を上げる、読者層の広げかた
こんにちは、樺木宏です。
さて、私はメールのアドバイスで、
「読者層を広げ、読者数を増やす」
ことを提案することが多いです。
というのは、読者数が少いと手を挙げる出版社も限られてしまい、採用確度が低いことが1つ。
もう1つは、例え企画が通っても、部数が少ない為ブランディング効果が低いためです。
そうなると集客効果や、講演依頼なども期待できず、次の出版の声がかかる可能性も低くなってしまいます。
ですので、もっと読者層を広げ、読者数を増やすことを、アドバイスする事が多いのですね。
例えば、ゴルフに関するノウハウや事例を元に、本を書きたいとしましょう。
それを、ゴルファーに向けてそのまま本にするのでは、読者が少ないので難しいでしょう。
でも下記のような本にすれば、どうでしょうか。
○「なぜ、エグゼクティブはゴルフをするのか? 」
-読むだけで、仕事と人生の業績がUPするショートストーリー-
http://goo.gl/4pgJvJ
ゴルファーだけに向けた本ではなく、一般のビジネスパーソンが興味を持って読めるよう、
工夫していますので、読者数が大幅に広がり、出版可能性も大きく上がっていますね。
実際、この本は過去ベストセラーにもなったそうです。
○「コンセプトのつくりかた」
- コンセプトが見つかれば、やるべき事の99%が決まる -
http://goo.gl/hlFKWL
この本は、任天堂でゲーム機開発に携わった著者が、業界外の一般の素人の読者に向けて書いた本です。
ゲーム業界のプロ向けに書いているのではなく、あえて「素人」に向けて書いていることが、
参考になりますね。
その事で、読者層を広げ、読者数を増やす事に成功しています。
いかがでしょうか?
同じノウハウや事例でも、
「読者層を広げ、読者数を増やす」
ことで、出版の採用確度を大きく上げ、あなたのブランディグ効果を高めることができますので、
この考え方を、ぜひ活用してみて下さい。
2015/09/30本を読みたくない人にでも買ってもらえる、企画のテーマの作りかた
こんにちは、商業出版コンサルタントの樺木宏です。
さて、この記事を読んで頂いている方は、
本を書こうと考えている人か、すでに書いている人だと思います。
そういう方が往々にして見落としがちなのが「一般読者の感覚」です。
ネットを見れば大抵のことは無料で分かりますし、それをスマホでいつでも出来てしまう時代です。
また、できればオフタイムはダラダラして過ごしたいものですから、本を読んで学ぶのは苦痛でもあります。
そんな中、本を買って下さいということは、
「お金を出してストレスある行為をしてください」ということでもあるのですね。
これはハードルが高い要求であり、意識が高い人には盲点になりがちです。
だから、雑誌やWebと同じように考えていては、出版の企画は通りません
雑誌のような「浅く広い」テーマでは読者のストレスをクリアーできないからです。
スマホで通勤時間で無料のWebで暇つぶしをするならよいが、お金を払ってまでは読みたくない、
というのが普通の読者の感覚なのですね。
だから商業出版のテーマは、読者の悩みを浅く広く刺すのではなく、
「狭く深く刺す」ことがセオリーです。
お金を出したくなくでも、ダラダラして本を読みたくなくても、
「それでも逃れたい苦痛を解放してくれるかも」
「こんな風になれたら素晴らしいな」
を刺激しましょう。そして、
「自分の悩みを解消してくれる、自分のためにあるような本だ」
「この悩みを解決できるなら本代を払って、ガマンして読もう」
と感じてもらうことが不可欠なのですね。
いかがでしょうか?
あなたの企画が、"本を読みたくない人にでも買ってもらえる"ためのヒントになれば、幸いです。
2015/03/11必ず商業出版が決まる3つのコツその(1)読者ニーズ
こんにちは、樺木宏です。
さて、必ず商業出版が決まる3つのコツと題して、
基本的な、しかしとても重要な出版ノウハウをお伝えしていきます。
第1回目の今回は、「読者のニーズ」についてです。
商業出版は売れるかどうかで採用の成否が決まります。
いくら素晴らしい内容でも、すごい実績のある著者でも、それを読みたい人がいなければ、
売れる事はありません。
だから企画を採用する側の出版社としては、まず最初にチェックするのがこの読者ニーズなのです。
当然、著者の側としても、出版企画書の中で、必ず押さえないといけませんね。
読者のニーズをアピールするには、2つのやり方があります。
カンタンなのは、同じテーマですでに似た本が出ていて、それが今売れている場合。
出版社も当然それを知っていますから、読者ニーズについては軽く触れる程度でOKです。
気をつけなければ行けないのは、類書が少なかったり、すでにピークを過ぎて枯れているテーマ
の場合です。
この場合は、具体的な想定読者の数と質を、出版企画書の中で、説得して行く必要があります。
その説得力が、企画を検討するかどうかを左右するでしょう。
なお、新人著者の方でありがちなミスは、読者ニーズを丁寧に説得すべきなのにも関わらず、
軽く流してしまうこと。
売れ筋のテーマでもないのに、読者のニーズに言及する事なく、自分の企画内容の説明に終始
してしまえば、企画はスルーされてしまいますので、ここは注意したいですね。
では、具体的にどうやって読者のニーズをアピールするか?と言う事ですが、
・数:その事で悩んでいる人の数は、本が十分売れるほど多いのか?
・質:その悩みは、お金を払ってでも解決したいほど深いのか?
の2つの要素が挙げられます。
ここを出版企画書の中で、十分にアピールしていきましょう。
数については、一般的には100万人の想定読者がいれば、採用確度はある程度高い、と考えて良いでしょう。
質については、まさに著者の経験や、力量が問われる所です。
「どのような悩みに注目して、読者を設定するのか?」
ここが、企画の半分を占めると言っても良いくらい大切なことですから、
じっくりと取り組みたいですね。
私が企画を一緒に考える場合も、かなりの時間をここで費やしします。
いかがでしょうか?
出版社がまず最初にチェックする、読者ニーズ。
出版企画を考える時は、ぜひ時間を割いて考案してくださいね。
2015/01/14商業出版の成否を左右する、たった1つの"視点"とは?
こんにちは、樺木宏です。
さて、商業出版では、あなたの企画が編集会議を通るか通らないか、そこが大事ですね。
私は過去4年で100冊以上の出版企画を通して来ましたが、
編集会議で企画を通す上で、大事だと感じている視点があります。
それは、
「この本は、読者にどんな新しい"得"を提供するのか?」
ということです。
これが明確になっていないと、まずその出版企画は通りません。
いくら素晴らしい実績のある著者で、売れているテーマの本だとしても、
「すでに似たような本が出ているから、もう売れないだろう」
と思われてしまうからです。
そう思われないために
「この本は読者にとって、こんなに魅力的で、新しい"得"がありますよ」
ということを、出版企画書でアピールする必要があるのですね。
その時注意したいのが、その"得"の内容です。
あまり高度な内容だと、読者は敬遠してしまいます。
それは優秀な著者だからできるので、自分にはムリだ、と感じさせてしまいますし、
もっと身近かな事に悩んでいるので、そんな高度な欲求は無い、という読者も多いのですね。
目線を下げて、あなたのレベルではなく、読み手のレベルに合わせることで、
"得"がより魅力的になり、読者にとっても、出版社にとっても、輝きを増してきます。
特に初めて本を出す人の場合は、知名度やファンの数で売る、というワザがつかえませんから、
本が読者に与える"得"の魅力は、そのままあなたの著者としての魅力ですから、
ここはぜひ押さえておいて欲しいです。
あなたの出版企画がさらに編集会議を通りやすくなるための、ご参考になれば幸いです。



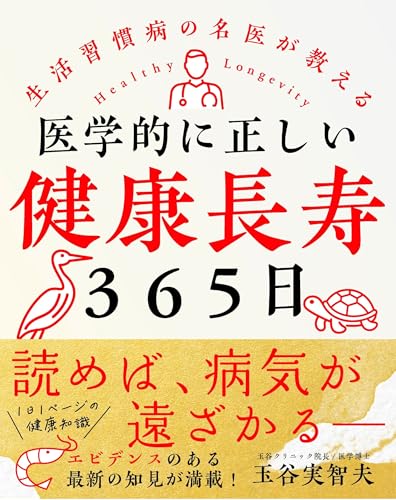
 読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
