あなたに隠された「著者の強み」に気づく
2013/06/10「出版企画が通りやすい人」に共通することとは?
こんにちは、樺木宏です。
今日の記事タイトル、これから本を出したい人、出し続けたい人は、当然気になる所ですよね。
出版企画が通りやすい人、というのは確かにいます。
あなたは何が要因だと思いますか?
知名度があるから?
実績がすごいから?
私がこの2年強で60冊以上の通してきて確信するのは、そのどちらでも無い、と言う事です。
知名度がある有名著者でも、企画が通らない人は大勢います。
実績がすごくても、なかなか本を出せない人もいます。
それ以前に大切なのは「自己開示」なのです。
というのも、出版企画を考えるというのは、ある意味自分の半生をさらけ出す、という側面があるから。
そして重要なことは、「強みは弱みの中にあることが多い」という事実です。
つまり、ここで躊躇してしまうと、自分のせっかくの強みを企画に活かせないのですね。
例えば、かつてとても貧乏だったが、今は成功している人がいるとします。
その人が、過去を隠してしまうと、「ただの成功者」です。
そんな人は世の中に大勢いるので、他の著者と差別化されません。
ということは、企画もユニークなものになりずらいので、なかなか通りません。
しかし、「貧乏のどん底から這い上がった成功者」ならどうでしょうか?
インパクトが格段に違いますね。
「そんなに低いところから這い上がった人の言うことなら、すごい内容なのでは」
という出版社の期待も高まりますし、
「そんな状態からでも成功できるのなら、自分にも出来そうだ」
という読者のメリットにも直結します。
このように、あえて弱みを自己開示することは、著者にとってとても大切なこと。
そして、本を出しやすい人に共通する特徴でもあるのですね。
あなたの自己開示はどうでしょうか?
2013/06/04自分を俯瞰で見れば、企画は必ずある
こんにちは、樺木宏です。
さて、この仕事を初めてから、約80冊の出版企画を通してきました。
その中でも売れている本に共通するのは、
「自分の強みを活かし、読者のニーズがあり、かつ類書と差別化されていること」
です。
この3ポイントは、何度かお伝えしていますので、以前から私の記事を読んで頂いているあなたは、
すでにご存知のことと思います。
とはいえ、私の見る限り、依然として9割以上の人は「自分の書きたい事」ばかりに焦点があたっています。
「自分の強みにはなかなか気づかないし、類書との比較もなかなか難しい」
こういう人がほとんど。
つまり、知識として分かっているだけでは、不十分なのですね。
では何がプラスアルファで必要かと言えば、
「自分を俯瞰で見ること」
です。
もっと具体的ないい方をすれば、人称を上げる、という事。
多くの人は、最初は「自分の書きたい事を書く!」という、「私」の段階。
これは1人称ですね。
そこに「読者」という相手を想定できる人は、2人称の段階。
誰の問題を解決しようか?と考えはじめればしめたものです。
そして最後に、「他の著者の本と比較してどうか?」とか、「今の時代このテーマはどうか?」
という比較、つまり3人称の段階になってきます。
ここまで自分を客観視できて初めて、
「自分の強みを活かし、読者のニーズがあり、かつ類書と差別化されていること」
を見つける事ができるのですね。
こうなれば、その企画は通る直前まで来ているといって良いでしょう。
あなたの人称は、何人称でしょうか?
もし、自分の人称が低い、と思っても、焦る必要はありません。
客観視できれば企画は通る、と分かった訳ですから、
そのスキルを伸ばすなり、第3者の客観的なアドバイスに耳を傾ければよいのですね。
人称を上げて、企画をグレードアップさせて行きましょう。
2013/06/04自分では気づかない才能に目覚める方法とは?
こんにちは、樺木宏です。
「強みを発揮すれば成功する」とは、本やセミナーで多く語られていることですね。
出版でも「どう書くか」よりも、「何を書くか」の方が圧倒的に大切です。
というのも、企画の内容がその人の人柄や強みと結びついていなければ、
強い企画になり得ないからですね。
自分自身に眠っている面白い企画のネタで、ベストなものは何か?
言い換えれば「自分の才能は何か?」を探すことは、成功する為の最初にして最大の、
重要事項と言っても良いかもしれません。
私の仕事も、ある意味その人の「才能探し」という側面が強いです。
なお、ここで言う才能とは「常に完璧に近い成果を生み出す能力」であり、
学習と経験によって得た知識・技術ではありません。
さて、かくも重要な「才能」ですが、具体的にはどのように探したらいいのでしょうか?
結論から言えば、才能を研究し、体系化している人や本に学ぶことが最短距離でしょう。
自分だけで考えていては、気付いた時には人生の残り時間わずか、と言う事にもなりかねません。
なぜかと言うと、もともと才能とは自分では気づきにくく出来ているからです。
「ポジティブ心理学の祖父」といわれるドナルド・O・クリフトンによれば、
「無意識に繰り返される思考・感情・行動のパターン」とのこと。
(参考:「さあ、才能に目覚めよう」日本経済新聞出版社刊)
自分では当たり前と思ってしまい、それが自分に特有のこととはイメージしずらいのですね。
実際、私も企画書にぜんぜん強みが書いておらず、会っていろいろ質問すると、
すごいものを持っていた、というケースが良くあります。
そうした時に皆さんが言うのは「他の人はそれやってないんですか?」です。
このように、自分では無意識にやっているので、当たり前すぎて強みに気づかないのですね。
上の参考文献などの書籍で「才能」について学ぶことは、人生にとって大変有意義な気付きを
あなたに与えることと思います。
ここで、才能についてもう少し詳しくお伝えします。
才能とは、繰り返される思考・感情・行動のパターンであることはすでにお伝えしました。
では、なぜこのパターンが生まれるか?と言う事ですが、その理由は脳細胞にあります。
脳細胞同志の結びつきは「シナプス」といわれる接合によるものですが、
その伝達の流れやすい経路が、一人一人異なるのです。
これが、いわゆる「才能」の正体です。
そして興味深いことに、そのシナプスは3歳までに回路が全て出来上がり、
16歳ごろまでに大半が壊れてしまうのです。
なぜかと言うと、回路を絞り込むことで、より高速で優れたものになるから。
もし絞り込まれず全ての回路が残っていたら、外界からの刺激が多過ぎて知覚機能が
マヒし、「概念」を持てなくなり、何かを感じたり、人間関係を築くことも出来なくなる
と言われています。
このように、才能とは大変重要なのですが、自分では気付きにくいものなのですね。
自分の才能に気付く事が、あなたの成功を加速します。
すでに深い見識のある、良書やセミナーで学びましょう。
2013/06/03本を出しやすい職業、本を出しずらい職業
こんにちは、樺木宏です。
世の中には、本を出しやすい職業と、そうでない職業がありますね。
本を出しやすい職業とは、知識を提供する系統のビジネスのこと。
例えば、コンサルタントや士業、コーチ、カウンセラーなどは、
日頃から「知識」を駆使して、お客の問題を解決しています。
本も、「知識で読者の問題を解決する」ものなので、そのまま本になりやすいのですね。
一方、本を出しずらい職業もあります。
それは、モノを売っていたり、場を提供したり、というビジネスの人。
こうした職種の場合、顧客との間に「モノ」や「場所」がありますから、
知識だけを提供しても、なかなか本になりずらいのです。
では、そうしたビジネスの人は、出版を諦めるほかはないのか?
決して、そんなことはありません。
なぜなら、「モノやサービスを、抽象化する」ことで、それは知識になるからです。
抽象化とは、本質を抜き出して残りは捨てること。
例えば、食品を販売するビジネスの人がいたとします。
抽象化すれば、
「体によい素材だけにこだわっている→健康を売っている」
となるかも知れませんし、
「大勢のひとに美味しい味を提供している→楽しい時間と、コミュニケーションを売っている」
となるかも知れません。
そして、抽象化されたものは知識ですから、書籍と相性が良くなります。
つまり、本が出しやすいテーマに変わるのですね。
いかがでしょうか?
もし本を出したいが、自分のビジネスでは難しいかも?という人がいたら、
ぜひ"抽象化"してみて下さいね。
2013/05/31"素人目線"という最強スキル
こんにちは、樺木宏です。
さて、著者を目指す人を見ていると、なにがしかの「専門家」な人が多いです。
士業やコンサルタント、経営者。
かれらは皆プロなので、高度なノウハウをもっています。
そして、その高度なノウハウに、価値の源泉があると思っている人がほとんどです。
だから、凄いノウハウをより凄く見せようとしています。
でも、これは"勘違い"なんですね。
本当に付加価値があるのはそこではないのです。
ではどこに付加価値があるのか?
それは、「素人目線」です。
その分野のノウハウについて何も知らない素人が、
"何を分かっていないか" が分かるスキル。
これが素人目線。
この素人目線はある意味、最強のスキルです。
なぜなら、平凡なコンテンツが、「世の中に求められるもの」に化けるから。
例えば、TVのゴールデンタイムの常連、池上彰さん。
よく経済や政治を語っていますが、かれはその道のNo.1でしょうか?
会社経営をしたことも無いでしょうし、経済学の権威でもありませんん。
政治家でもありませんし、政治評論家でもありません。
もっと詳しい人や、語る資格のある人は大勢いるでしょう。
でも、なぜ池上さんだけが、ゴールデンタイムにひっぱりだこなのか?
それは、「素人のツボを知っているから」言い変えると、素人に「なるほど!」
と言わせるのが飛び抜けて上手いからですね。
そうなると、「それなら聞いてみたい」「難しそうで敬遠していたが実は関心があった」
となります。
世の中の求めているものに変わる→数字が取れる→ひっぱりだこ
なのですね。
これは、書籍の著者も同じです。
権威が無くても、実積が無くても,素人目線というスキルがあれば、
コンテンツは「世の中に求められるもの」に化けます。
例えばドラッカー本で一番売れたのはドラッカー本人の本ではなく、「もしドラ」。
この本の著者は、マネジメントのエキスパートではなく、元放送作家、つまり素人目線のエキスパートでしたね。
そう考えると、あなたが次に見つけるべきは、さらなる専門性ではなく、
"素人目線"なのかもしれません。
ここに気付だけで、情報発信者としてさらなる飛躍が出来る人も多いですよ。



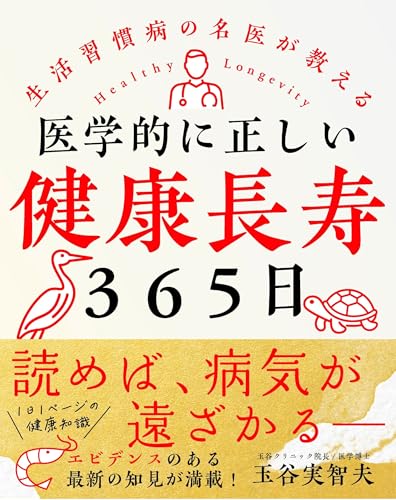
 読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
