あなたに隠された「著者の強み」に気づく
2016/06/15思っているよりも価値がある、あなたの○○とは?
こんにちは、樺木 宏です。
さて仕事柄、著者さんの強みを見いだし、出版企画に反映する、ということを繰り返しているのですが、
「こんなに素晴らしいものを持っているのに、なぜ自分では気づかないのか?」と不思議になることがよくあります。
私から見たら、「ぜひそれを活かして、テーマの中心にしましょう!」
くらいの勢いなのですが、
「えっ、そんなことが凄いんですね」
というような感じで、はじめて聞いた、ような顏をする方が多いのです。
それもそのはず、人間の脳というのは、とてもエネルギーを消費する器官なので、
「当たり前」をつくりだして、省エネしてしまいがち。
普通の人なら、そうなんだ、で終わって良いのですが、
あなたが出版企画をつくろうとするとき、強みを見落とさせてしまうのですから、
著者としてはぜひ気をつけたいところですね。
特に気をつけたいのは、自分自身の経験や主観を、過小評価してしまうことです。
例えば、読者と同じ悩みを克服したこと。
これは著者としては、読者の共感を得られるだけでなく、書く資格を出版社に証明する実績であり、
臨場感のある事例を豊富に持っているという強みもであり、確信に満ちた文章を書く原動力にもなります。
例えば、自分の意見が他人と違うこと。
同じような内容の本が多い中で、それは独自性という強みになります。
出版社からみれば新しい切り口であり、読者からみれば視野を広げてくれる本になります。
例えば、過去残念だった時期があること。
そうした過去は隠してカッコいいことだけ書きたい著者が多い中で、
それは裏表の無い人、読者を励ます人、というブランディグになり、
企画の説得力を高める材料にもなります。
ほかにもいろいろとあるのですが、上記は本当によくある例として、お伝えしました。
脳はあなたの強みを覆い隠してしまうもの。
そこを打ち破って強みを引き出し、あなたのベストの書籍を作り出して下さいね。
ご参考になれば幸いです。
2016/06/08"振りきった主張"が売れる本になる
こんにちは、樺木 宏です。
さて、企画を考えたり、本を書こうとすると、周りの目が気になるものです。
なかでも、「関係各位や業界に睨まれたらイヤだな・・・」という思いは、
誰しも胸に去来するのではないでしょうか?
こうしたとき、注意すべきことがあります。
それは、当たり障りのない、無難な内容になってしまわないか、ということです。
「こんな事を言ってしまったら、○○を敵にまわすのでは・・・」
と感じてしまうと、誰しも守りに入るもの。
しかしそれでは、読者の心を揺さぶらない本になってしまいます。
売れる企画にも、売れる本にもなりませんので、実に勿体ないことです。
逆に、自分の保身や関係各位に配慮するのではなく、徹底的に読者のために書とどうなるでしょうか?
その本は、間違いなく読者に刺さります。
例えば、この本です。
「成功する転職5%の法則」──プロが教える転職の「真実」http://goo.gl/9wIyjY
転職を考えている人向けに、業界のウラ側から正しいやり方を教える本です。
かなり業界の暗部を暴露してしまっていますので、同業者からは快く思われない可能性がたかいのですが、
逆に読者にしてみれば、これほど親身になって、本当の事を教えてくれる本はありません。
「自分の為の本だ!」と共感してもらえる本なのです。
だからこそ、企画も通りましたし、読者からも、そして心ある業界関係者からも、評価が高いのですね。
いかがでしょうか?
ぜひ無難な内容になることなく、読者のために「尖った」内容にしてください。
ご参考になれば幸いです。
2015/10/14著者プロフィールで"証明"すべきこととは?
こんにちは、商業出版コンサルタントの樺木宏です。
さて、出版社に企画を提案するときは、かならず「著者プロフィール」の欄があります。
ここを何となく書いてしまうと、通る企画も通らなくなりますので、注意が必要です。
というのも、著者プロフィールには大事な「証明すべきこと」があるからです。
「なぜすでに本を出してるベテラン著者ではなく、新人のこの人に執筆を依頼すべきなのか?」
という疑問をもっているのが、普通の出版社側の視点です。
経験豊富な著者に依頼した方が進行のリスクもなく、売れ行きも過去のデータが
あって安心なのに、なぜあえて新人に頼むのか?
ここをクリアーするために、「このテーマを語るに相応しい経験、実績、ノウハウを持つ人だ」
と証明する必要があるのですね。
ここ意識して書かないと、「これだったらベテランに頼んだ方がよい」となってしまい、
企画の評価が高くても執筆依頼が来ない、という残念なことになってしまいます。
ただ、安心して欲しいのは「全てにおいてライバルより優れている、と証明する必要はない」という点です。
あくまで「このテーマに限定して」でよいのですね。
例えば、ダイエット本であれば、特定の年齢層については強みがある、
女性向けのノウハウは平凡でも、「中高年男性」に限定したならば強みがある、
というような見せかたで十分です。
それだけで「中高年に向けた本の著者としては」十分な経験、実績、ノウハウを持つ人だ、
ということで、出版社側も安心してあなたに執筆を依頼してくれるでしょう。
いかがでしょうか?
著者プロフィールでは、"限定"して"証明"して、
あなたの企画の採用確度を高めて下さいね。
ご参考になれば幸いです。
2015/04/01必ず商業出版が決まる3つのコツ、その(3)ポジショニング
こんにちは、樺木宏です。
さて、前々回から、必ず商業出版が決まる3つのコツと題して、
基本的な、しかしとても重要な出版ノウハウをお伝えしていきます。
第3回目の今回は、「著者の強み」についての続きです。
前回例に挙げたのが、こちらの本です。
http://goo.gl/fAFo05
新人著者ながら2冊の出版を同時に決めた著者の毛利優子さんは
・どのように強みを活かしたのか?
・なぜ出版社から好評価されたのか?
について、お伝えしたいと思います。
まず、どのように強みを活かしたのか?という事ですが、
ポイントは、
「強みを複数考え、最も有利な立ち位置を取れるものを選んだ」
と言うことに尽きます。
人の強みとは、1つではありません。
見方を変えると、いくつもの強みがあるものなのです。
しかし多くの人は、ひとつ思いついてしまうと、それに執着してしまいがち。
毛利さんの場合はそうではなく、そこからさらに複数考えて行き、ライバル著者の状況や、いまの売れ筋テーマ
などとも比較しながら、最も有利な位置をとれる立ち位置を選んだのですね。
先の例で言うと、仕事と家庭の両立をテーマにした本は多いです。
毛利さんもその強みを持っているのですが、強いライバルが先行しており、相対的に不利。
そこで他の強み、
>最初の就活から子供がおり、3人の子供を育てながら働いた経験に加えて、
>仕事では働くママ向けのWebサイトを企画立案・運営した実績
に注目しました。
それを一歩手前のテーマ、つまり仕事と家庭の両立以前に、そもそも良い仕事に復帰できない、
という不安に焦点を当てれないか?と調べてみると、そこにはライバル著者が少ない、
良いポジションが空いていました。
具体的には、女性の約6割が出産後に退職してしまう現在の日本。
25~54歳女性の平均就業率は69%と低く、OECD加盟国34ヵ国中24位です。
ですが皮肉な事に、実は約8割の母親が「何かしらの職に就いていたい」とも考えています
そこで必要とされるのは、育児と両立できる職に就くこと。
しかしそうした情報は少ないです。
"家庭と両立するための仕事術"の本は多いのですが、
そもそも「家庭と両立できる仕事」をどうやって見つければ良いのか、
そこに焦点を当てた本がなかったのですね。
こうして、自分の強みを複数把握しつつ、市場と比較して、有利なポジションを探していくことで、
ご自身の強みも活かされ、ライバルも少ない、
有利な立ち位置を取れたことが、成功した要因です。
結果、3社の出版社からオファーをもらい、2冊の出版を同時に決めることができたのですね。
読者の需要があるのに供給が少ないのですから、その好評価も当然、ということです。
いかがでしょうか?
あなたがご自身の本を出版されるとき、強みは1つではありません。
客観的に、複数の強みを把握すること。
それを市場の需給バランスに合わせて、柔軟に組み合わせていくこと。
そのことで、商業出版の成功だけでなく、その後のビジネスも大きく飛躍するのですね。
2015/03/25必ず商業出版が決まる3つのコツ、その(2)著者の強み
こんにちは、樺木宏です。
さて、前回から、必ず商業出版が決まる3つのコツと題して、
基本的な、しかしとても重要な出版ノウハウをお伝えしていきます。
第2回目の今回は、「著者の強み」についてです。
よく「今こういう本が売れているから、こういう企画はどうでしょう?」
という相談を受けるのですが、そのままでは難しい場合が多いです。
それというのも、「あなたならではの強み」がその企画に活かされていない場合が多いから。
出版社は、いわば誰に頼んで書いてもらってもよい立場ですし、売れ筋のテーマはよく研究しています。
だから"あなたに書いてもらうべき理由"がないと、よりベテランな著者を探してきて
先に頼んでしまう、ということになってしまうのですね。
例えば、「女性の働きかた」というテーマでは、すでに先行している著者さんが大勢います。
その中にはTV等のメディア露出も多く、知名度が高いベテラン著者も含まれます。
そうした中に、売れているからといって、強みを活かさずに飛び込んでしまっては、
まず企画は通りませんし、通っても売れない本になってしまうでしょう。
さらには、仮に買ってくれた人がいても、強みが活かされていない本では、
ビジネスに誘導した際、ライバルのサービスの方が良く見えてしまい、選んでもらえない、
という事が起こってしまいます。
ではどうするか?という事ですが、
その一例が、こちらの本です。
http://goo.gl/fAFo05
先の「女性の働きかた」というテーマで、新人著者さんながら、2冊の出版を同時に決めた方です。
・どのように強みを活かしたのか?
・なぜ出版社から好評価されたのか?
そのことについては、次回に詳しくお伝えしたいと思います。



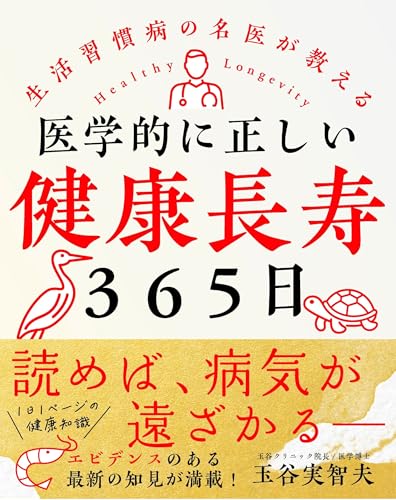
 読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
