不安が消える、知識武装編
2017/03/15はじめての出版では、『著者<読者』と考えよう
こんにちは、樺木宏です。
はじめて出版して本を出そうと考えると、どうしても肩に力が入ってしまいますよね。
その気持ち、よく分かります。
なにしろ題材は自分の半生ともいうべき、経歴や実績、そして大切なノウハウです。
思い入れも強いでしょうし、「これを書きたい!」「こうやって伝えたい!」
というこだわりも沢山あるでしょう。
ただ、こと商業出版となると、すこしコツが必要になってきます。
その思い入れをそのまま直球で投げても、なかなか出版が決まらなかったり、
決まってもあまり売れないことが多いのです。
それはなぜかと言うと、
「出版社は"売れるかどうか"が判断基準だから」です。
言い換えると、著者の基準で「素晴らしい」と思える本よりも、
読者の目線で「売れる!」と思える本を、もとめているのです。
このお互いの意識のズレは、商業出版の企画に決定的な影響を与えます。
例えば、出版社は多くの人が読めるわかりやすい本をもとめているのに、
著者がプロも唸るような通好み向けの本を書こうとする。
あるいは、著者が自分自身の、高度な自己実現欲求で本を書こうとして、
日々の暮らしに悩む読者を置いていってしまう。
もしくは、多くの人が手に取ることがわかっているテーマを避けて、
読み手の人数が不明な、ニッチなテーマの本を書こうとしてしまう。
こうしたズレが起きてしまうと、まず出版社に企画が通りませんし、
たとえ通っても売れないのです。
そうならない為にも、自分の思い入れも大切にしながらも、読者も大切にして考える。
つまり最初の商業出版では、『著者<読者』と考えるくらいでちょうど良いのです。
肩に力が入ったとき、ぜひこれを思いだしてください。
バランスの取れた企画を考案し、著者として大きく前進していきましょう。
2017/02/01お坊さんが教えてくれる、企画を通す"奥義"とは?
こんにちは、樺木宏です。
さて、先日とても参考になる商業出版のノウハウに出会いましたので、シェアしたいと思います。
アルボムッレ・スマナサーラさんという、原始仏教の僧侶の方のご著書から、以下引用です。
>指摘されたところは、修正してしまえばいいのです。そうしているうちに、
>だんだん欠点を指摘することができなくなって、結局は企画を通してしまうことになります。
>ちょっとずるい方法のように聞こえるかもしれませんが、実際には理性的な方法です。
>人間の心理的な部分を利用した方法です。
>なぜなら、人間は誰でも、他人のしていることにケチをつけたくなるのです。だから、
>こちらから、悪いところを教えてくださいという態度に出れば、何も言えなくなってしまうのです
「仕事でいちばん大切なこと」アルボムッレ・スマナサーラ著 より
いかがでしょうか?
僧侶の方なのに、企画にも精通していてすごいですね。
私などはこれを読んで、まさに奥義、と思ってしまいました。
というのも、
「商業出版で本を何冊も出せる人と、なかなか出せない人の違い」は、
まさにここにあるからです。
最初の本をあっさり出せる人、その後も何冊も出している人は、一言で言えば、
「出版社に企画をダメ出しされる"前"に、企画をブラッシュアップしている人」です。
そして、なかなか本を出せない人はその逆で、
「出版社に企画をダメ出しされるまで、企画をブラッシュアップしなかった人」なのです。
私は今までにおよそ160冊以上の商業出版の企画を通してきましたが、上記は「法則」と言っていいほど、
再現性があるノウハウだと考えています。
とはいえ、人間には感情がつきもの。
一生懸命考えた企画を変えるのは、抵抗がある人もいるでしょう。
特に、すでに一定の成功を収めた経営者や、有名大学の学歴を持つ方には、そうした抵抗が大きいようです。
逆に、とても柔軟で素直な思考の人は、抵抗なく企画をブラッシュアップしていくので、
あっさりと商業出版が決まったり、何冊も出し続けたり、ということが普通に起こります。
あなたはどちらのタイプでしょうか?
ぜひこの僧侶の方の考え方を取り入れて、著者としての"煩悩"を振り払ってくださいね。
ご参考になれば幸いです。
2016/12/14「企画を通す苦労」はすべきか否か?
こんにちは、樺木(かばき)宏です。
あなたは出版社から、出版企画を却下された経験があるでしょうか?
「何度も却下されているよ」という人もいるでしょうし、
「意外とすんなり通った」という人もいるでしょう。
苦労は買ってでもせよ、ということわざもありますが、
私は「企画を却下されるストレス」は、あまり経験しない方がよいと考えています。
というのも、気持ちが落ちこんでしまい、行動しずらくなってしまうからです。
出版企画というものは、自分自身のノウハウだけでなく、思い入れもこめた大切なもの。
それを却下されてしまうと、「自分には著者になる能力が欠けているのでは?」という疑念が生まれます。
それはとても大きなストレスなので、「もう感じたくない」ということで、企画を考えなくなったり、
出版社に提案することをやめてしまいたくなるのです。
たとえ打たれ強い人でも、何度も何度も却下されていれば、遅かれ早かれ、同じような状態になってしまいます。
私はむしろ逆に、
「企画が意外とあっさり通ったな。やっぱり自分はデキる人間だ」
と思ってもらうのが、理想的だと考えています。
エジンバラ大学のジョンソン博士によれば、
「自己の能力を(たとえ過信でも)高く評価する人は、競合に対して有利になり、集団のなかで優位に立ちやすい」
ことが証明されているそうです。
だから、本を出そうという人は、自信過剰なくらいでちょうどよい。
逆にそうした天狗の鼻が折れないように、注意すべきなのです。
とはいえ、過信だけで企画が通るほど、商業出版は甘くはありません。
そこは事前の準備を、謙虚に行うことも大切。
事前に何度も何度も企画を練り、いわば事前にダメ出しして、本番の採用確度を上げることは言うまでもないでしょう。
「練習は謙虚に、本番では天狗になる」
これがベストですね。
とはいえ、「悔しさをバネに」できる場合もあるでしょうから、
それはそれで活かしていきましょう。
不要なストレスはあまり感じることなく、ぜひ著者のキャリアの好スタートを切ってくださいね。
2016/11/30ちょっと待った!その本、まだ出してはいけません
こんにちは、商業出版コンサルタントの樺木宏(かばき ひろし)です。
さて、本は早く出せば出すほど良い、と思っていませんか?
確かに時間は有限ですから、早く出すほうが、メリットが多い面もあります。
しかし、実はすぐに本を出すことは要注意なのです。
なぜなら、商業出版で本を出すことは、「拡声器」をつかうようなものだからです。
それが良い声であれ、悪い声であれ、拡大されて多くの人に伝わってしまいます。
それが十分練られた、納得のいくものなら良いのですが、そうでない場合、取り返しがつきません。
例えば、「ライバルと比べていないケース」。
これは一番陥りがちなワナです。
あなたの本より先に多くの本が世に出ているのですから、それと比較することは不可欠。
そうでないと「いままでの本と似たような企画」というレッテルを貼られてしまい、
企画が通りませんし、仮に通っても「二番煎じの著者」になってしまいます。
あるいは、「自分の強みを客観的に掘り下げていないケース」
せっかくの強みをスルーしてしまい、本に反映していない人が実に多いものです。
自分の強みというものは、自分ではなかなか分かりません。
これには理由があって、脳は極力省エネをしようとするので、
良く知っていることは、いちいち「すごい」と思わず「当たり前」と感じさせるからなのですね。
そして、「今かけることをそのまま書くケース」。
これも、ありがちなワナです。
自分の業務内容や専門領域の内容を、そのまま周囲の向けに書くイメージがあると、
読者を狭めてしまいます。
いかがでしょうか?
このように、十分ポテンシャルを活かしていない企画や本が、実に多いもの。
この記事を読んで頂いているあなたには、ぜひこうした落とし穴を避け、
「今書けるベストの出版企画、そして本」を作り上げて欲しいと思います。
2016/11/02なぜ著者の学歴は、"中卒"が最強なのか?
こんにちは、樺木宏です。
さて、今回の記事のタイトルは、
「なぜ著者の学歴は、"中卒"が最強なのか?」。
違和感を前面に押しだした疑問系のタイトルにしてみました。
これはべつに煽ったり盛ったりしているわけではなく、
私は本当に「中卒」が最強だと思っています。
それはなぜか?
なぜなら、「落差」が大きいため、インパクトと説得力が大きいからです。
例えば、ビジネスパーソンなら誰もが名経営者として知っている、松下幸之助さん。
小学校を中退して9歳で丁稚奉公に出て、苦労して今のパナソニックの礎を築き上げた
エピソードはとても有名ですね。
松下幸之助さんの「道をひらく」という本は200刷、500万部を突破している、超ベストセラー&ロングセラーです。
ここでもし、松下幸之助さんが有名企業の御曹司だったとして、良い教育を受けて良い大学にいき、
親から会社を継いでいたらどうでしょうか?
例え同じ能力があったとしても、ここまで尊敬されてはいなかったでしょう。
500万部を超えてまだ本が売れ続ける、とういことも無かったはずです。
その証拠に、日本に大企業はパナソニック以外にも多く、名経営者も著者大勢いるにも関わらず、
ここまで尊敬され、本が売れている人はなかなかいません。
その違いの1つに、語る内容もさることながら、小学校を卒業して丁稚奉公という「落差」があるのは間違いないでしょう。
大きなインパクトを生み、語る内容の説得力が高まっているから強いのです。
そういう意味で、学歴は低ければ低いほど、尊敬されます。
今の日本の教育制度では中学校まで義務教育ですから「中卒」が最強、なのですね。
あなたがプロフィールをつくる際も、良い点ばかりを並べるのではなく、
こうした「落差」を上手くつくれると、インパクトと説得力を高められるので、
ぜひ工夫してみて下さい。
なお、大切なのは「低さ」ではなく「落差」。
その後の成長や実績がないと、落差が生まれませんので、そこはしっかりと押さえてください。
あなたの著者としてのブランディグの、ご参考になれば幸いです。



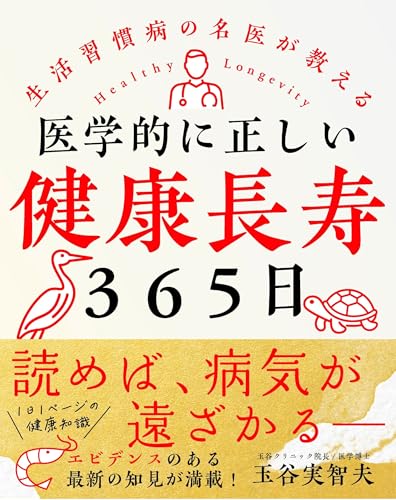
 読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
