不安が消える、知識武装編
2018/11/22著者なら必ず知っておきたい、"検索の落とし穴" とは?
こんにちは、保護ねこ9匹と暮らす出版コンサルタントの、樺木宏です。
さて、「検索」といえば、もはや生活に欠かせないものとなりました。
仕事でもそうですし、本を書くということにおいても、とても便利なのが「検索」です。
ただ、最近とても実感するのは、
「検索に頼りすぎると、著者としての可能性が狭くなってしまう」
ということ。
たとえば最近、
「どこかで聞いたことがある」
ようなアウトプットが多くありませんか?
たしかに検索は便利なので、調べものをしたり、広く浅く知るには、向いています。
でも逆にいえば、多くの人がやっていることなので、
アウトプットが皆似かよってしまいがち。
著者としては「似たようなことばかり書く人」と思われてしまっては、
ブランディング的に大きな損失なので、ここは注意したいところですね。
ちなみにベストセラーを数多く出しているとある出版社は、
編集会議であえて書店のPOSデータを見ないようにしているところもあります。
やはり売れている本の検索結果を見てしまうと、プロですらどうしても似たような本に
なってしまう、ということなのでしょう。
余談ですが、私が2年前に書いた「幸せになりたければ ねこと暮らしなさい」という本、
ねことの暮らしを脳科学や心理学、そして社会学の知識と組み合わせた内容です。
このような内容は検索しようにも当時なかったので、
読者からすれば「なんだこれは!?」というサプライズを感じてもらえたことも、
ベストセラーになった一因だと思っています。
さて、話しをもどしましょう。
検索のデメリットについて、お話していました。
あなたは最近、
「例え話がつまらない、あるいは無い本」
を買ってしまい、読み進めるのが苦痛だったことはないでしょうか?
検索は、いきなり「結果」が出てくる分、その過程を飛ばしてしまっています。
変わったことを考えたり、意外な組み合わせを試してみたりといったプロセスを
経ることがないので、過程の話しが無い、あるいはつまらないアウトプットになりがち。
ここも著者の基準として、チェックしておきたいですね。
お金を出して情報を買ってもらうのが、著者という仕事ですから、
その説明の面白さや、説得力こそが大事なところなのです。
このように、「検索」は便利な反面、クオリティの高いアウトプットする上で、
じつは落とし穴もあるのですね。
あなたが商業出版レベルのアウトプットをし続けていくのなら、
検索するまえに、
「モヤモヤ自分で考えること」
も大事にしていきましょう。
人はつい考えるステップを飛ばしてしまいがちなので、
これを心がけるだけでも、半分うまくいったようなもの、
と言っても過言ではないでしょう。
あなたのアウトプットのクオリティを更に高めるための、ご参考になれば幸いです。
2018/11/08当たり前だけどなかなか気づかない、ベストセラー著者になるコツ
こんにちは、保護ねこ9匹と暮らす出版コンサルタントの、樺木宏です。
さて、この記事を読んで頂いているあなたは、
熱心に商業出版のノウハウを学んでいる方でしょう。
それは、とても素晴らしいことだと思います。
が、しかし。
それだけでは、不十分なんですね。
「えっ、じゃあなんでこんな記事書いているの?」
というツッコミがのどまで出かかったかたも、そうでないかたも、
私の体験談を聞いてみてください。
私は数年前に、「ねこ」をテーマにした自己啓発書を書きました。
幸い、関係各位の方々のご助力もあり、8万部のベストセラーとなりました。
そのとき、私は思ったものです。
「出版のノウハウがあってよかった」と。
でもそのあと出した2冊目の本は、1冊目と違って、売れませんでした。
そして、実感したんですね。
出版ノウハウがあるからベストセラーになったのではなく、
それを「ちゃんと使った」から、ベストセラーになったのだということに。
あとになって考えてみれば、2冊目の本は、1冊目と比べて、
出版ノウハウを「使う」時間が短かったです。
決して手を抜いたわけではありません。
むしろ以前よりも、時間はかけていました。
にもかかわらず、さまざまなノウハウがあり、頭ではわかっていながらも、
それという自覚もないままに、「これで十分だろう」となっていたのです。
つまり、
「知識は簡単に感情に負ける」
ということです。
知識だけは不十分、というのは、こういうことなのですね。
そしてここに、なかなか気づかない「ベストセラー著者になるコツ」もあります。
これを知っていると、ポテンシャルを生かし続けることができます。
出版ノウハウだけがいくらあっても、感情がそれを邪魔します。
そして人間は、感情の生き物。
だから、自信があるときこそ、
「もっとこう考えてみたらどうか?」
というクセをつけておくことです。
「いい企画が思いついた!」とか、
「このアイデアなら売れる!」とか、
自信があるときほど、落とし穴が見えないもの。
そんなときは、ぜひ今回の記事を思い出し、
軽々と穴を飛び越えていきましょう。
2018/11/01アイデアが"ひらめく"ために必要な、たった1つのこと
こんにちは、保護ねこ9匹と暮らす出版コンサルタントの、樺木宏です。
アイデア1つで、本がだせてしまうのが商業出版。
全国にあなたの名前が書かれた本が書店に並び、
ブランド力や集客力が高まる上に、印税までもらえるのですから、
いいアイデアを思いつきたいですよね。
でも、そうは言っても、
「なかなか思いつかないよ」
という声も聞こえてきそうです。
その気持ちは、よく分かります。
一方で、どんどんアイデアを思いつき、本を出し続けている人もいます。
こちらの気持ちも、私はわかります
その差を分けるのは、何なのでしょうか?
実は、誰もが知っていて、単純なこと。
それは、
「モヤモヤ」
することです。
これを避けないことが、よいアイデアを思いつくためには、
絶対に欠かせません。
他の仕事に置き換えてみると、わかりやすいと思います。
例えば、あなたの仕事の新商品開発。
「モヤモヤ」せずに、
らくらくベストなアイデアが浮かんできて、
誰からもなんのツッコミみいれられず、
そのまま商品にGOサインがでて、
しかも大ヒット。
・・・こんなことがあったでしょうか?
ないですよね。
こんなことは誰もが知っていることですが、
不思議なことに、こと「自分の本を出す」ことになると、
そうした知識や経験が、どこかにいってしまいがちなのです。
最初に思いついたアイデアをなかなか手放せないのは、モヤモヤに逆戻りするのがイヤだからです。
企画のブラッシュアップがおっくうなのも、モヤモヤするのが不快だからです。
その結果が、実績もノウハウも持っているのに「いつかは本を出したい暦3年以上」という人が、
これほど多い現状なのですね。
ということは、逆にいえば、「モヤモヤ」という状態を、
乗り越える方法があればよい、ということ。
これにはいろいろな方法があるでしょう。
意思が強い人なら、強引にモヤモヤする時間をつくるのもよいでしょう。
それはちょっと辛いという人なら、スキマ時間をつかって、
例えば歩いている時にモヤモヤ考える、というのも効果的です。
あるいは、筋トレのジムに通う人の理由と同じく、
「そうしなければいけないように、スケジュールに入れてしまう」
のもありですね。
私にコンサルの依頼を申し込んでいただくかたは、この動機も大きいようです。
やりかたは人それぞれ。
1つ言えるのは、「モヤモヤ」を避けてしまっては、よいアイデアは出ない。
だからそれを、習慣に取り込んでしまうことですね。
それが習慣になってしまえば、もう大丈夫。
いくらでもアイデアを思いつく、土壌ができたといえるでしょう。
あなたの人生を変えるアイデアが浮かぶための、ご参考になれば幸いです。
2018/06/212018年の今、本を出そうとすることのメリットとは?
こんにちは、保護ねこ8匹と暮らす出版コンサルタント、樺木宏です。
さて、出版不況といわれて久しく、発行点数も減りつつある近年。
業界が縮小する中で、著者が紙の「本」を出す意味は減っているのでしょうか?
結論から言えば、むしろ本を出す意味は「増している」と、私は考えています。
たとえ1冊あたりの売れ行きが落ちてきても、
1冊あたりの賞味期限が短くなってきても、です。
なぜなら、情報の発信者は「二極化」していくからです。
誰もが情報発信できる時代だからこそ、飽和し、選ばれるのは難しくなります。
メルマガでも、流行りはじめは誰でも読者を増やすことができましたが、今はとても難しい。
ブログやSNSでも、それは同じです。
情報発信さえすれば読んでもらえる、という時代はもう戻ってこないでしょう。
実際、出版業界でも以前よりも安易に本を出すのは難しくなりました。
しかしその一方で、1部の人は、以前よりも注目されやすくなる人たちがいます。
それが、著者です。
情報が増えすぎて、受け手も選びきれない。
だから「今選ばれているのは何か」という、他者の判断が注目されます。
出版社というハードルを越えないと出せない、商業出版は、
プロの目利きによって「選ばれた情報」という価値があります。
ラジオや雑誌、Webなどの媒体では、著者から取材しよう、という傾向はむしろ強まっているように感じます。
ドラマやアニメの原作でも、書籍が元になっているケースも増えているようです。
そう考えると、書籍の発行点数が減っていくことは、
むしろ著者にとっては有利なことなのですね。
逆に、こうした時代に割を食ってしまうのが、「中間」の情報発信者。
そこらにあふれた情報よりもよほどいい情報発信をしているものの、
埋もれてしまって受け手に届かない。
あるいは、ライバルも多くて、先に誰かが選ばれてしまう。
二極化の時代は、中間にいるとうだけで、大きなリスクを抱えているのですね。
だから何かの特色を見いだし、尖らせて、読者のニーズに深く刺す。
そして「著者」という付加価値を得て、より選ばれやすいポジションを取る。
これが今の時代、有効な立ち位置の取り方。
ご参考になれば幸いです。
2018/06/07商業出版と自費出版、3つの見分け方とは?
こんにちは、保護ねこ8匹と暮らす出版コンサルタント、樺木宏です。
さて、世の中にはいろいろな出版のカタチがあります。
出版社が費用を全て負担し、販売後に営業や広告まで打ってくれる「商業出版」。
著者が費用を出し、販促や流通についても著者の負担になってしまう「自費出版」。
前者は出版社が売る努力をしてくれますが、後者はそれがありません。
だから同じ出版と名がついていても、著者が得られるブランディグの効果は、天地の差があります。
ではこの出版の違い、見分け方を知っていますか?
時と場合によっていくつか簡単な方法があるので、いくつかお伝えしましょう。
まず、出版のオファーがきたときに見分ける方法は、
「どっちがお金をだすか」。
どんなに呼び名が違っていても、この1点を見れば、必ず見分けられます。
なお、「商業出版と自費出版を両方やっている」タイプの会社というのもあります。
なので、それが商業出版か自費出版かは一瞬分かりにくいのですが、
あなたがお金を出版社に払うなら、それはどんな出版社からのオファーであっっても、
たとえ「自費出版ではない」と言われたとしても(企業出版、協力出版などが一般的な別名です)、
呼び名が違うだけの自費出版です。
次は、本を見て、その本が自費出版かどうかを見分ける方法です。
本の表紙を見てみましょう。
出版社名が書かれていますね。
ネットで出版社名を検索すれば、自費出版専門の出版社はすぐ分かります。
分かりずらいのは商業出版「も」やっている出版社の場合ですが、
多くの場合は出版社名の後に、「ちょっとひと言」が加わっています。
業界内で流通する際、商業出版のラインではないことを示す必要があるため、
そうなっているのですね。
だから、社名になにかひとことでも加わっていれば、その本は自費出版と判断してよいでしょう。
そして、本の内容からも、違いを見分けることができます。
その見分け方とは、
「自分を向いた本」は自費出版。
「読者を向いた本」は商業出版です。
慣れてくるとタイトルを見ただけで、文字通り「一瞬」で分かるようになるものです。
言い換えれば、自費出版というのは「趣味」なのです。
自分のこだわりや表現欲を優先しているので、
読者に対しての学びを分かりやすくまとめたり、
再現しやすいように工夫したり、という配慮が少ない。
対して商業出版は、「仕事」です。
文字通り「ビジネスとしての出版」ですから、お客=読者の欲求を満たさなければ、
仕事として成立しません。
だからあの手この手で分かりやすく、親切にいろいろと工夫するのですね。
このことは、見分けるだけでなく、あなたが本を出すときの
「最高のヒント」でもあります。
何を書こうか、どうか書こうか考えるとき、
「これは誰の欲求を満たす本なのか?」
「自分の強みで、うまく欲求を満たしてあげられないか?
「似たような本と比べて、もっと欲求を満たしてあげる工夫が出来ないか?」
と考えることができたなら、商業出版は近いです。
たとえ今のあなたのノウハウが普通でも、実績が少なくとも、
こういう考え方ができれば、本を出す最短距離を行く事ができます。
逆に言えば、どれだけノウハウや実績があっても、
それが「趣味」ならば、本がなかなか出せないし、例え出しても売れないのです。
いかがでしょうか?
商業出版と自費出版、3つの見分け方。
あなたの著者活動のヒントになれば幸いです。



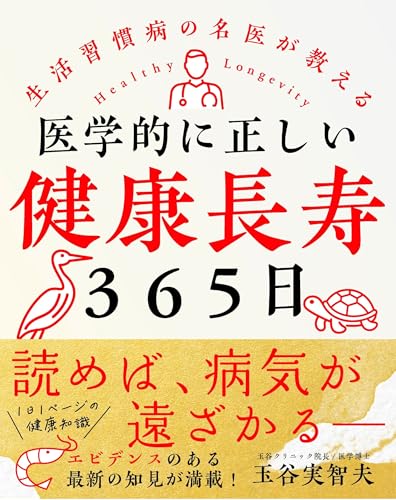
 読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
