不安が消える、知識武装編
2016/10/26今知らないことも、あなたの執筆ネタになる
こんにちは、樺木宏です。
さて、本を出したいとは思うものの、
「200ページもの量は書けないのでは?」とか、
もう本を出していて、
「さらに本を出すネタはもう残っていない」
という人は多いものです。
一方で、本を10冊、20冊と出し続ける人がいるのも事実。
この違いはどこから生まれるのでしょうか?
それは、
「今は知らないことを書く」
という考え方を知っているかどうかの違いです。
例え書きはじめたときは全てを知らなくとも、新たにインプットしながら、情報をアウトプットしていく、という事ですね。
こうする事で、あなたが書ける内容は大きく広がりますし、読者により有益な本を届けることにもつながります。
実際、ベテラン著者がオファーを受ける際は、このように新しいインプットをするものです。
執筆依頼を受けてから、本を大量に買い込んで勉強する、という人もいます。
ここで、「本というのは、自分の知識を書くものでは?」
と思われるかも知れませんね。
その場合は「成長しながら書き続ける」と考えて見て下さい。
考えてみれば、新人著者のときに最初から「本を10冊書いてください」といわれて、書ける人はほとんどいません。
でも1冊本を書き、それにともなって多くのインプットが生まれ、あらたな学びがあり、考え方も進化し・・・
と、徐々に成長しながら、いつのまにかベテラン著者になっていくものなのです。
そう考えると、「新たに学びながら、成長しながら、今知らないことを将来書く」
というのも、すんなりと腑に落ちるのではないでしょうか。
また、しっかり読むということは、考えることにも直結しています。
本を読みながら着想を得たり、アイデアが閃いたりすることもよくあるものです。
そういう意味でも、たとえ知っていることでも再度インプットするのは意義あることですね。
堂々と、今は知らないことも視野に入れて、本を出し続けていきましょう。
2016/10/19自分の本への"勘"があてにならない理由
こんにちは、樺木宏です。
自分の本を出すというのは、人生の中でも大きなイベントですね。
その分思い入れも強くなりがちですが、ここで気をつけたいことがあります。
それは、
「あまり自分の勘を信じない方が良い」
ということです。
思い入れに水を差すようですが、この考え方は本当に役立ちますので、
商業出版の企画を通し、より売れる本をつくるために、あえてお伝えしたいと思います。
なぜ自分の勘を信じない方がよいのか?
それは、どうしても自分のことは客観視できないからです。
思い入れの強さは、悪い面を隠し、良い面ばかりを意識してしまうことにも繋がります。
それは今の読者が求めているものを見えにくくさせますし、
ライバルの本との差別化を考えるときには、邪魔になります。
さらには、著者さん自分自身の中にあるる「本当の強み」も、見えなくさせてしまいます。
私はよく「こういう本を書きたい」という相談を受けるのですが、
それがその人の書けるベストの企画であることは1%以下です。
今まで150冊以上の商業出版の企画を通したうち、著者さんが最初に考えた企画がそのまま通った例は1冊しかありません。
残りの149冊以上はどうやって通したかというと、著者さん本人も気づいていなかった「ベストの企画」を探したのです。
その人が書けるあらゆる企画の可能性を全て考え、それに優先順序をつけ、可能性の高いものから企画にしていく。
こういうプロセスを経る事で、著者としての成功確率は飛躍的に高まるのですね。
いかがでしょうか?
自分自身というのは、1番客観的に見れないもの。
ぜひ一度立ち止まって、成功への最短距離を歩いていきましょう。
2016/08/10ブランド力を高めたい人のための、本を出し続ける出版術、
考え方その3:読者の側からも考える
こんにちは、樺木 宏です。
さて、シリーズでお伝えしている商業出版の企画ノウハウ、今回は第6回目。
優れた知識や経験を持つ人は多いものですが、著者は少ないですね。
「こんなにいい内容なのに、なぜ売れないのか、企画が通らないのか」
と思っている人は多いのではないでしょうか?
その差は「読者のことをどれだけ親身になって考えるか」の違いにあります。
例えば、本を書こうという人は、自分らしさを表現したい、
ということが動機になっていたりするので、自己実現の欲求が強いです。
対して読者の多くは、
「会社にいくのがイヤだな」
とか
「将来のお金をどうしよう」
といった安全欲求であったり、
「会社周りと仲良くやりたい」
という親和欲求が強かったりします。
この欲求のズレは、「書きたい本と売れる本のズレ」そのものです。
この溝を埋めないかぎり、いかに優れた知識でも、売れる本にはなりません。
そして読者はあなたのレベルには合わせてくれませんので、あなたの方から読者に歩み寄る
必要があります。
それができるかどうかが、著者としての成否を分けます。
言葉で言うとカンタンなのですが、実行しようとすると難しいのがこの「歩み寄り」。
なぜなら、そうした企画は一見レベルが低く見えてしまうことがあるからです。
そうなると、周囲の人に「たいした事が無い」と評価されてしまうのが怖くなります。
なので、読者に歩み寄るには、勇気がいるのですね。
しかしそこで一歩踏み出せるかどうかが、決定的な差になるのです。
言い換えれば、「私が」という一人称から、「読者は」という二人称に変われるかどうか。
その視点を持てれば、今ある素晴らしい知識や経験が、売れるコンテンツに変わります。
私がクライアントさんにアドバイスする中で、そうしたマインドブロックを外すのは、
初期の大きな仕事の一つです。
ぜひ読者のレベルに歩み寄り、著者としての大きな一歩を踏み出して下さい。
2016/08/04ブランド力を高めたい人のための、本を出し続ける出版術、
考え方その2:ライバルも利用する
こんにちは、樺木 宏です。
さて、シリーズでお伝えしている商業出版の企画ノウハウ、今回は第5回目です。
結論から言えば、ライバルを利用すると、本を出し続けることが容易になります。
その理由は3つあります。
それぞれ説明していきましょう。
1)売れていない切り口は避けて通ることができる
「これは良いアイデアだ!」と思っても、残念ながら出版社に受け入れられないことはよくあります。
せっかくのアイデアを企画にするために、投入した時間やエネルギーが無駄になるのは勿体ないですね。
それが続くと、本を出すこと自体を諦めてしまうことにも繋がります。
そこで、ライバルを利用しましょう。
ライバル達がすでに出している本を見れば、どういう切り口が売れて、どういう切り口が
売れないのか、が見えてきます。
時間の短縮とエネルギーの節約になり、精神衛生上も助けになります。
2)空いているところを探すことができる
そうやって数をみていくと、ライバル達が何を書いているかだけでなく、
「何を書いていないか」が見えてきます。
それが、あなたが書くべきテーマになることはよくあります。
売れている中にも、まだ書かれていないテーマは、差別化されている可能性が高いもの。
これが見つかるのも、大きなメリットです。
3)類書にツッコミをいれることで企画案ができる
ライバルの主張を読んで行くうちに、
「自分ならこう書く」という意見や反論がでてくるでしょう。
これが、そのまま新しい企画の主張になることが多いです。
それをメモし続けていれば、目次案をつくっているのと同じになります。
自然と企画が形になり、企画考案のスピードも何倍にもなります。
いかがでしょうか?
ライバルを利用すると、本を出し続けることが容易になります。
ぜひ行動に移して見て下さい。
2016/07/20ブランド力を高めたい人のための、本を出し続ける出版術、
考え方その1:使えるものは全部つかう
こんにちは、樺木 宏です。
さて、シリーズでお伝えしている商業出版の企画ノウハウ、今回は第4回目。
今回からは「考え方編」です。
同じような力量でも、かたやベストセラー著者になり、かたや1冊も本が出ない。
こんなケースはよくあります。
本を出せる人とそうでない人の違いは、力量ではないのです。
ではなにがその違いを生むのか?
それは「行動量の差」です。
たとえ最初は力量が足りなくとも、本を出すべく行動しているうちに、いろいろな情報がインプットされてきます。
今の読者がどういうことに悩んでいるか。
ライバルはどんな本を出しているか。
こうした情報が入ってくるので、だんだん企画が良くなっていきます。
最初は残念だった企画が、短時間で見違えるように変わってきます。
また、あなたも気づいていない強みが見つかることも多いです。
出版業界の側から、忌憚の無いフィードバックが来るたびに、
自分を客観視することに繋がるからです。
このように、行動している人としていない人では、いつのまにか差がついているものです。
だから「活かせる機会は全部活かして、使えるものは全部使ってとにかく行動する」
というのが、著者への最短距離となる考え方なのです。
特に大切なのが「人脈」です。
ノウハウも、チャンスも、全て人脈が運んできます。
特に出版はそうです。
編集者、先輩書著、そして出版プロデューサー、こうした機会は使えるのは全部使いましょう。
編集者は強力な味方ですが、彼らも企画の質にサラリーマン人生がかかっていますので、
無理押しは禁物。
相手の立場も考えて、相談したいものです。
先輩著者も、良いアドバイスや人脈を繋いでくれるでしょう。
ただ、そのノウハウがいつのものか?その人自身の実績はどうなのか?
は必ずチェックしましょう。
出版のトレンドやマーケティングの動きは速いので、古い情報は害になることも多いです。
出版プロデューサーは、時間を短縮し、一気に飛躍できる機会を提供します。
ただ、力量は見極めたいですし、囲い込みはされないようにしましょう。
このような点に注意してください。
使える人脈は全て使う、という考え方で行動すれば、必ず成長、結果に繋がってきます。
ぜひ、参考にしてみてください。
(もし以前の「心構え編」をまだ読んでいない方はバックナンバーもどうぞ)
心構え編その1 http://goo.gl/lz58EN
心構え編その2 http://goo.gl/fBSBHY
心構え編その3 http://goo.gl/0Oh56o



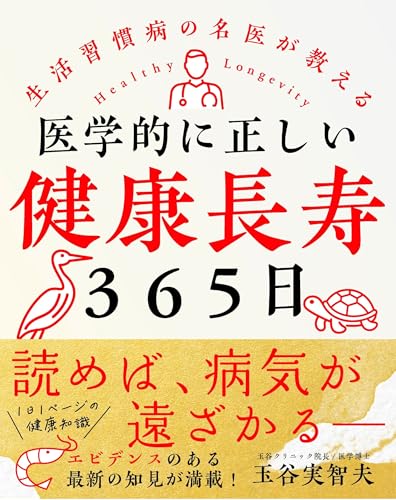
 読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
