不安が消える、知識武装編
2014/06/27「客観視」と「柔軟性」という2つの強力な武器
こんにちは、樺木宏です。
ちょっと想像してみて欲しいのですが、
株式投資をしている人がいて、
「世の中の多くの人が何といおうと、自分がこの株が良いと思うから、とにかく買う」
という人がいたら、いずれ損するというのはすぐ分かります。
相場というのはいわば人気投票なので、他の人の影響を必ず受けるからです。
相対的に価値が下がってしまうことは、自分ではコントロールできません。
さて、株だとお金の話なので分かりやすいのですが、
「商業出版」となると、これが感情的に分かりにくくなってしまうもの。
思い入れがとても強くなるのが普通ですから、どんなに優秀な人でも、
自分の専門分野ではするはずのないミスを、出版だとついしてしまうのです。
例えば、
「自分がこの内容は有意義だと思うから、ぜひこの内容で書きたい」
という考え方が、まさにこれです。
その理由は、上記の株の話と同じ。
本の評価も、相対的な部分が大きいからです。
「ライバルの著者はどんな事を書いているか?」
「そしてそうした内容について、多くの読者はどのように評価しているか?」
こうした視点が抜けていれば、一見もっともそうにきこえても、当たり外れは運次第の博打になります。
そして出版企画書では、この企画は博打なのか、しっかり狙いすましたものなのか、
それが編集者には、ハッキリと見えてしまいます。
博打だと思われたら、その企画はそこまで。
そうはなりたくないですね。
自分の企画に思い入れを持つ事はとても大切ですが、
そこに「客観視」という武器が加われば、鬼に金棒。
そして「柔軟性」まで持てば、その人は本を出し続けることが出来る、と断言します。
ぜひこの2つの武器を意識して、著者デビューへの最短距離を走り抜けて下さいね。
2014/06/17長く読み続けられる本を書く、という事
こんにちは、樺木宏です。
長く売れる本、つくりたいですね。
しかし現在の出版業界は、出版点数は高止まりしており、逆に市場としては縮小傾向。
こうなってくると、1点1点の重さは軽くなってしまいます。
そうした中で、長く売れる本、長く読み続けられる本を書くのは、とても難しい事です。
そんな中で、私がコンサルティングの際に心がけていることがあります。
それは、
「すぐに具体的な答えを提案せず、あえて考えてもらう」
という事。
相談を受けると、頭の中に、現状で最も売れそうな企画はすぐ浮かびます。
それをすぐ企画書にするのは、スキルさえあれば、ある意味簡単なことです。
でも、あえてそれをせずに、「もう1歩先」を考えてもらうようにしているのです。
なぜなら、すぐ役に立つことは、すぐに役に立たなくなるからです。
そうした本を、大量に見てきました。
今の時代、出版のトレンドは数ヶ月で去ります。
一時期流行に乗って本が売れても、それが去ってしまえばあとは何も残らない。
残らないならまだよい方で、かつての自分が忘れられずに、逆に落ち込んでしまう人も多い。
安易にトレンドに迎合した結果がそれでは、あまりに悲しいですね。
そうならない為にも、
「自分自身の熱いメッセージ」
「自分でも明確に意識できていなかったコアな主張」
といったものを、ここで考えておきたいのです。
人柄や熱さが行間から伝わる本になれば、例え一時の喧騒は去っても、本質はそこに残ります。
そして、それは読者に伝わり続けるのですね。
それが、長く売れる本にも繋がって行くのだと思います。
全ての本を後世に語り継がれる本にするのは難しいとしても、せめてそうした
「読者の琴線に触れる何か」
は必ず残していきたいですね。
2014/03/21"最初の出版"のテーマの決め方
こんにちは、樺木宏です。
さて、商業出版に関するノウハウも、いろいろと出回っていますね。
しかし大きく異なるのが、"戦略面"。
つまり、著者のブランディグ戦略です。
ここは考え方がいくつもある、という事はぜひ知っておいた方が良いと思います。
ここを間違えてしまうと、文字通り著者人生を大きく左右してしまう為、
後悔することもあるからです。
特に私は「人生で最初の1冊を支援する」というスタンスなので、ここにはこだわりがあります。
例えば、「1冊目の本のテーマをどうやって決めるか」というときに、
「最初の本のテーマは一生ついて回るから、自分のビジネスと直結させろ」、
という人がいます。
確かにメリットとしては、今のビジネスに「箔」がつきますし、
読者がそのまま顧客になってくれるので、集客的にも良いでしょう。
でも、ちょっと待って下さい。
それがあなたに当てはまるかどうかは、別の話です。
例えば、あなたの今のビジネスが、ベストかつ唯一の選択なのか?ということです。
他にももっとやりがいがあり、人脈を活用でき、ノウハウも発揮できる、
そんなビジネスの切り口が隠れているかも知れません。
もしそうだとしたら、先の考え方は、近道のように見えて、遠回りになってしまいます。
特に、出版社からオファーがくる場合は、要注意です。
出版社が見ているのは、今うれるかどうか。
著者側の中長期のブランディングについては、ほとんど考えていないことの方が多いです。
いかがでしょうか?
商業出版の戦略には、いろいろな考え方があります。
「そのノウハウがあなたに当てはまるかどうか?」は、熟考してみて下さいね。
2014/01/07マラソンのようにインプットすれば、勝手に良い企画になる
こんにちは、樺木宏です。
さて、本を出し続けたい、と思うのは著者ならば誰しも同じです。
そして良い本を書く為には、読書やセミナーなど、良いインプットを継続することが大切。
これはだれもが分かっている事なのですが、
実際は、それを実現出来る著者と、そうでない著者に別れてしまうのも事実です。
なぜそのような違いが生まれてしまうのか?
それは、
「インプットは、短距離走ではなく長距離走」
と言うことを、あまり意識していないからだと思います。
1冊出せればそれでよい、という短距離ならば、"息を止めてひたすら頑張る"でも良いのですが、
実際は、本は出し続けたいもの。
マルコム・グラッドウェルの「1万時間の法則」によれば、
「世界で通用する人間に共通するのは、一万時間の練習を続けている事」。
つまりマラソンなのですから、短距離走のつもりでは息が続きません。
なのに、感情に逆らって、ストレスを感じながら頑張ると、どうしてもやる気の波がおきてしまう。
やる気が下がった先には、挫折もありえます。
そうではなく、時には水分を補給し、コンディショニングしながらペース配分をする必要があります。
・少しペースを落としてでも、確実にコツコツ前に進む
・もう少しやりたい、くらいであえて止める
・ペースの目安になる集団に参加してみる
などなど、です。
その先には、今はまだ見えない成長の境地が待っています。
その為にも、マラソンのように、インプットし続ける。
ぜひあなたも、ペース配分をしつつ、良い企画を量産し続けてください。
2013/11/29行動し続ければ、出版できる3つの理由
こんにちは、樺木宏です。
「どうやったら商業出版できるか?」という質問を受けることは多いです。
そういう場合私は、
「行動し続ければ、結果は出ます」
と答えるようにしています。
たとえ今自信がなくても、実績が少なくても、です。
なぜなら、それには3つの理由があるからです。
1つには、企画力がついてくるから。
2つ目は回数が増えれば、単純に確率が増すから。
3つ目は、周りが応援するからです。
まず1つ目ですが、企画力がついてきます。
なぜなら、「企画が通らない方法がまた1つ体得できた」事になるからです。
知識は使って初めて体得できるもの。
いくら出版企画セミナーで知識を得ても、繰り返し使って行かなければ身に付きません。
逆に、使って行けば、例え企画が通らないことが合っても、本当の企画力が身に付いていくものです。
次に2つ目。提案回数が増えれば、比例して出版の確率があがるからです。
それというのも、編集者の数だけストライクゾーンは微妙に違っているもの。
過去ベストセラーになった本が、何十社も断られている、という話は珍しくありません。
100万部を超えたベストセラーでも、最初は何回も断られた、という話はザラです。
だからこそ単純に、数をこなして行けば、可能性は高まるのです。
そして3つ目、周りの応援です。
熱意は伝わり、伝搬します。
それは編集者に影響を与えますし、私も同様です。
例えば、私は預かった企画は、必ず複数の出版社に提案しています。
そうすると、編集者も覚えているもので、別の企画を持っていくと、
「あのときの、こういう企画の人ですね」という話になります。
接触回数の増加が、好意や安心感につながり、採用に影響する事もよくあるのです。
逆に、行動していない人だと、熱意もあまり伝わってきません。
そうなると、上記のような追い風は吹いてこないのですね。
いかがでしょうか?
結論はシンプルです。
「行動し続ければ、結果は出ます。
皆さんの指針として、ご参考にしてみて下さいね。



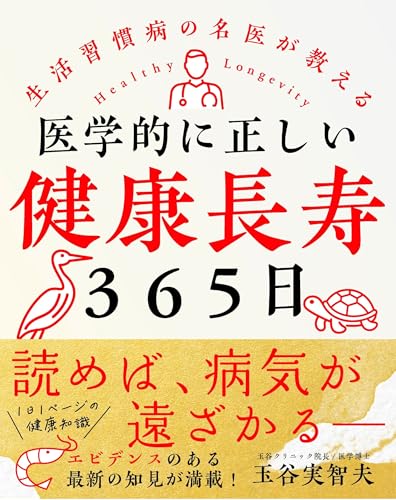
 読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
