不安が消える、知識武装編
2023/04/06共感の時代の、本の書き方
こんにちは。
保護ねこ8匹と暮らす出版コンサルタント、樺木宏です。
さて、本を出版しようという方は、経験も実績もある方が多いです。
年齢層も比較的高くなっていく傾向があるのですが、そこで問題が1つ。
それは、
「昔の本と今の本は、本のかき方がけっこう違う」
ことです。
この違いに気がついていないと、
「今の時代に売れる本」にならないので、出版社に企画がなかなか透りませんし、
仮に販売力などでカバーして本を出しても、売れない本になりやすいです。
では、どう違うのか?ということですが、
一番大きいのは、
「上から目線で教えるのではなく、寄り添ってシェアする」
ということでしょう。
今の時代は共感の時代と言われていますし、
コーチングなどの啓蒙も進んだ結果、
まずは相手の意見や考えを聞くのが先。
正しいことをそのまま教えるティーチング的な書き方では、読者に受け入れられにくくなっています。
しかし著者はその道の専門家ですし、
自分が何も分からなかった時のことは忘れてしまっていますから、
ストレートに正しいことを教えがち。
そうなると、読者は「お説教されているようだ」と感じてしまいます。
また教える順番も、
「読者が理解しやすい順番」ではなく、
「知識がある人が心地よいと感じる、体系化された順番」で教える傾向があります。
そうなると「とっつきにくい。ストレスを感じる」という印象を、読者に与えがちです。
このように、
「昔の本と今の本は、本のかき方がけっこう違う」
のですね。
言い換えると、
「著者のほうから、読者目線に寄り添う」
のが、今の時代の本の書き方です。
他にも、文字数が減っているとか、文章を細かく区切ってテンポよくしている、
などの細かい違いはありますが、いずれも「著者と読者の目線の高さ」に付随するものです。
もしあなたが経験も実績もある方で、売れる本を出そうと考えているなら、
ここは外せないポイント。
逆にいえば、このポイントを押えれば、
あなたの著者としてのポテンシャルを、もっと活かすことが出来ますよ。
ご参考になれば幸いです。
2023/03/02脳のせいにするのをやめよう
こんにちは。
保護ねこ8匹と暮らす出版コンサルタント、樺木宏です。
現在7万部を超えているベストセラー、
川手鮎子さんの「漢方の暮らし365日」を読んでいて、
気になるフレーズがありましたので共有しますね。
それは、
「脳のせいにしない」
というものです。
仕事をしているとイライラしたり、
プライベートでも憂鬱な気分になることがありますよね。
これらは西洋医学的には「脳」のせいにされることが多いのですが、
漢方では「五臓六腑に責任がある」ということなのです。
確かに心を整える「幸せホルモン」セロトニンは、
その9割以上が腸でつくられていますし、
身体を動かせば気持ちが晴れるのも、誰しもが経験していることですね。
そう考えると、
商業出版でよい本を出したいとか、
世の中の悩める人の問題を解決してあげたいとか、
自分のブランディングをしようといった、
「前向きな気持ち」も、実は大部分が身体のコンディション次第、
と考えたほうが理にかなっているようです。
なんでも脳のストレスのせいにしても、解決しなくていつまでも反芻思考をくりかえすくらいなら、
栄養や運動の知識をアップデートしたほうが、よい著者になれる。
ご参考になれば幸いです。
2023/02/23すごい経歴は必要ない
こんにちは。
保護ねこ8匹と暮らす出版コンサルタント、樺木宏です。
商業出版で本を出そうとすると、
「もっとすごい実績が必要なのでは...」
と思いがちですが、あなたはいかがでしょうか?
結論から言えば、その考えは半分正しく、半分間違っています。
正しい部分というのは、
その専門知識を語る上で、必要最低限の経験や実績は必要、ということです。
ただあくまで必要最低限であって、
決してすごい必要はありません。
そして間違っている部分というのは、
「すごい実績なら、読者が受け入れてくれるだろう」
というものです。
これはむしろ逆のことが多い。
なぜなら、実績がすごければすごいほど、
「この人だから出来るのであって、自分には同じことをするのは無理だろう」とか、
「上から目線でお説教されたらイヤだな」など、
警戒してしまうものだからです。
逆に、「自分はこの程度でした」とカミングアウトしてしまったほうが、
「自分にもできそうだ」と感じてもらいやすいものです。
いかがでしょうか。
言い換えると、自分が受け入れてもらえるかどうかを気にすることは、
読者目線で企画を考えることとは関係がないのですね。
商業出版では、あくまで読者が主役。
そこで励まし、促し、再現性を高めてあげれば本の魅力も格段にアップしますよ。
ご参考になれば幸いです。
2023/02/16趣味は商業出版のテーマになりうるか?
こんにちは。
保護ねこ8匹と暮らす出版コンサルタント、樺木宏です。
商業出版で本を出そうとすると、まずは自分の仕事をテーマにすることを考えますね。
たとえば、
医師であれば、健康本。
ビジネスパーソンであればビジネス書。
法律の専門家であれば、その実用書。
などなどです。
一方、趣味はなかなか本のテーマにはならないと言われています。
というのも、商業出版の本は読者の問題解決のために書くためで、
仕事であれば何らかの形で他者に貢献していますが、
趣味は自分のためにやるものですから、読者のためになりにくいのです。
と、ここまでは一般論ですが、
私の考えはちょっと違っていまして、
「仕事と趣味をかけあわせると、いい本になる」
と考えています。
なぜなら、自分の仕事をテーマに本を書きたいという人は多すぎて、
似たような本がすでにたくさん出ているからです。
出版社は後から似たような本を出しても売れないと考えますから、
なかなか企画が通らないか、通っても売れない本になりやすいのです。
一方、趣味はというと、確かにそのままでは読者のメリットになりにくいのですが、
その過程で培われた経験やエピソード、考え方などは活かせます。
むしろあなたならではのオリジナリティがある、強みとも言えるのです。
こうして、
「読者ニーズはあるが、差別化できていない」仕事のテーマと、
「読者ニーズは無いが、差別化できている」趣味のテーマを組み合わせると、
「読者ニーズがあり、かつ差別化もできてきる」本が生まれる可能性があるのですね。
たとえば一例を挙げますと、
拙著「幸せになりたければ ねこと暮らしなさい」は、
そうした組み合わせの例になります。
「ねこが好き」という趣味の領域と、
「いろいろな本に接している」という仕事の知見を組み合わせて、
「ねこと暮らすことの素晴らしさを、いろいろな知見から説明する本」
になっています。
このように組み合わせることによって、
読者ニーズと差別化を両立することもできるのですね。
ちなみにこの本は10万部近いベストセラーになりましたので、
商業出版としても通用する考え方なのは実証済みです。
いかがでしょうか。
趣味はそのままでは出版のテーマにはなりませんが、
組み合わせて使えばとても強力な著者の武器になりますよ。
ご参考になれば幸いです。
2023/02/09本を書くことは、お説教の真逆です
こんにちは。
保護ねこ8匹と暮らす出版コンサルタント、樺木宏です。
商業出版の著者というと、一般的には「なにやらすごい専門家」というイメージがありますね。
実は、それはあなたが本を出すレベルに至った後でも同じです。
過去のイメージが自分の中にあるので、
「正しい内容を、権威を持って伝えよう」
と、つい肩に力が入ってしまいがちなのです。
その結果どうなるかというと、
「良い内容なんだけど、上からお説教されているような気になる」
「正確なんだけど、、今一つわかりにくい、腹落ちしない」
という印象を読者に与えてしまいます。
一方、商業出版ではライバル著者がしのぎを削っていて、
書店には親切で親しみやすい本が溢れています。
そうなると、読者はそちらの本を手に取るでしょうし、
そう考えた出版社は企画をなかなか通してくれない、ということになってしまうのです。
そうならない為には、
「著者」「本を出す」
といった言葉へのイメージを変えてしまうのがおすすめです。
権威があるからといって、親しみやすくてはいけないわけではありません。
考えてみれば、書籍といえども、結局は読者と著者のコミュニケーションです。
コミュニケーションなのであれば、
「親しみやすく、親切で、相手の気持ちを想像しながら伝える」
のは、仲良くなる上では当然の工夫ですね。
そうやって読者と仲良くなる行為が、売れる本を書くということです。
いかがでしょうか?
「正しい内容を、権威を持って伝えよう」とするのではなく、
「親しみやすく、親切で、相手の気持ちを想像しながら伝える」ことで、
あなたの著者としての印象も、生みだすコンテンツも、
ガラリと変わること請け合い。
ご参考になれば幸いです。



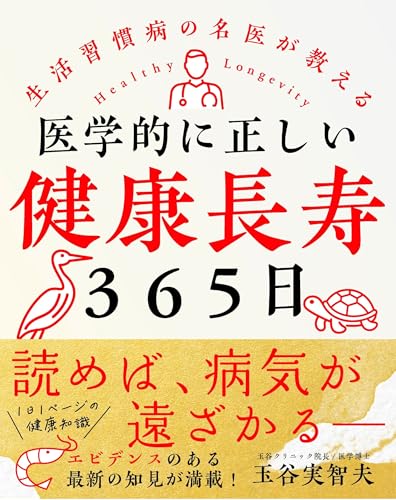
 読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
