あなたも出版できる!心構え編
2025/10/23自分には書けることがない、と思ったら
こんにちは、
保護ねこ8匹と暮らす出版コンサルタント、樺木宏です。
商業出版で本を出すというと、
「すごく成功している人がすること」
というイメージがありませんか?
誤解を恐れずいえば、それは勘違いなのです。
というのも、
「本は読者のためにあるもの」
だからです。
ここで、
「成功している人の方が、読者の役に立つことをたくさん書けるのでは?」
と疑問に思う人も多いと思います。
でも、それも勘違いです。
なぜなら、
「成功すればするほど、自分が成功していなかったころの感覚が失われる」
からです。
このことは、チップ・ハースさんの「アイデアのちから」という本に書かれています。
下記流用してご紹介しましょう。
---
これが「知の呪縛」というやつだ。いったん何かを知ってしまったら、それを知らない状態がどんなものか、うまく想像できなくなる。(中略)そうなると、自分の知識を他人と共有するのは難しい。聴き手の気持ちがわからないからだ。
専門家というのは、ニュアンスや複雑さに魅力を感じるものだ。そこに「知の呪縛」が生じる。(中略)そうなると単純明快なメッセージを書くことがただの「白痴化」に思えてしまう。
---
いかがでしょうか。
成功しているからといって、すごい知識やノウハウがあるからといって、
読者の役に立つ本を書けるとは限らず、むしろそこから遠ざかってしまうことの方が多いのです。
このことは、成功した人の「自費出版」でどんなことのが書かれているかを見れば、一目瞭然。
自慢話など「自分」に焦点が当たっていて、読者への配慮は皆無な本ばかりです。
逆に、「失敗」こそが、最高の執筆ネタになることは多いです。
というのも、成功は環境や運の要素が多く、再現性が低いのに対して、
失敗は、そうした要素に左右されにくく、再現性が高いからです。
つまり多くの失敗を経験している人ほど、読者にとって価値のあるコンテンツを提供できる。
しかも、読み手の気持ちが分かるので、それを共有するのも有利になる。
そういうことなのですね。
いかがでしょうか。
あなたがネガティブにとらえていた経験や知識ほど、
実は商業出版に最も適したネタかもしれません。
新たな視点で、棚卸ししてみてはいかがでしょうか?
2025/06/19いつかは本を出したい...が「今」に変わるコツ
こんにちは、
保護ねこ8匹と暮らす出版コンサルタント、樺木宏です。
「いつかは本を出したい...」
とは、よく聞く言葉ですね。
でも残念ながら、その「いつか」が、いつまでも「今」にならない人も多いです。
確かなノウハウを持っているのに、
逆境を乗り越えた素晴らしい経験があるのに、
なぜか、一歩を踏み出せない。
そして、
「もう少し準備をしてから...」
「もう少し実績を増やしてから...」
と、時間が過ぎていく。
とてももったいないことだと思います。
では、なぜ一歩を踏み出せないのか?
それは、
「他人の目を気にしてしまうから」
です。
せっかくいい知識や経験があっても、
その判断基準を他人に委ねてしまうと、なかなか決断できなくなります。
「ダメ出しされたらイヤだな...」
「よい本を書いて褒められたい」
「ぜひベストセラーにしたい!」
など、いずれも一見悪いものではありませんが、
基準が自分の中に無いので、迷いや不安が生じてしまうのです。
ではどうすれば?ということですが、
「基準を自分自身の中に置く」
ことが、力強く一歩を踏み出すために役立ちます。
たとえば、
「あのとき苦しんでいた自分に、一冊だけ本を渡せる」
としたら、あなたは何を書くでしょうか?
きっと、自分の中から「これを書きたい!」という熱い想いが湧いてくると思います。
他人にどう思われるかなんて二の次で、そんなことで不安になったりはしないでしょう。
もちろん、
「もう少し準備をしてから、実績を増やしてから...」
などと躊躇することもなく、すぐにでも書き始めることができるはずです。
いかがでしょうか?
あなたの本の判断基準は、あなたの中にあります。
いつかは本を出したい...が「今」になるための、ご参考になれば幸いです。
2025/05/29"初心"が最高の原動力になる
こんにちは、
保護ねこ8匹と暮らす出版コンサルタント、樺木宏です。
商業出版というと、なにやらハードルが高いイメージがないでしょうか。
たしかに、そういう面もあります。
出版社からOKが出なければ本が出せませんし、
多くの本の後から出版するためには、新しいプラスαも必要です。
そうした出版の知識が増えてくると、ハードルが高くなったように感じて、
心細くなってしまうかもしれません。
でも実は、一番大切なことを、あなたはすでにもっています。
それは、
「なぜ本を出そうと思ったのか?」
という初心です。
たとえば、
・こういう悩みで苦しんでいる多くの人を助けたい
・世の中のしくみで、納得いかないところを改善したい
などなど。
「義憤」といいかえてもいいでしょう。
こうした動機が、出版では最高の原動力になります。
出版のハードルが高く感じて「自分にも本が出せるのかな?」と不安になっても、
この初心に戻れば、再びエネルギーが湧いてきます。
出版社から企画を却下されて落ち込んでも、
「困った人を助けたい」という利他の気持ちが、再びチャレンジする原動力となります。
また本の内容も、読者に寄り添ったものになり、
読者からみれば、
「自分のためにあるような本だ」
「この本を知人にもすすめよう」
といった好印象を与えますし、
出版社からみれば、
「売れる本になりそうだ」というポジティブな評価にもつながりますから、
採用確度もアップすることでしょう。
いかがでしょうか。
もしあなたが商業出版いついて不安に思うのであれば、
細かい出版ノウハウに悩むのはいったん脇に置きましょう。
そして、
「初心」「義憤」「動機」
こうしたものにいったん立ち返ってみてください。
エネルギーが再び湧いてきて、出版が近づくこと請け合いです。
2025/03/13あなたの"動機"が一番大切
こんにちは、
保護ねこ8匹と暮らす出版コンサルタント、樺木宏です。
商業出版は、いろいろと要求が多い出版です。
出版社が費用を出しますので売れることが必要ですし、
読者にお金を払って買ってもらう以上、内容についても一定以上のレベルが求められます。
また表現面でも、先に優れた本が多数出版されていますから、新たな価値を提供することも大切です。
このように要求多い商業出版ですが、
実は一番大切なことは、それらのいずれでもありません。
それらよりもずっと大切なのは、
「あなたの動機」
です。
なぜなら、本の背後にある動機は読者に伝わるから。
そしてそれが、
「あなたはこういう人です」
という世の中のイメージを、作り上げるためです。
たとえば、過去の逆境から得た学びを本にする場合。
おなじテーマでも、
「同じ過ちを繰り返す人を減らしたい」という動機で本を書くのと、
「そんな逆境を克服した自分の凄さを自慢したい」のとでは、
まったく違う本になります。
動機が前者であれば、読者はあなたを「大切な学びを与えてくれた人生の先輩」だと感じるでしょう。
後者であれば、「なんかマウントを取ってくる人だな」と、煙たく思ってしまう可能性が高いです。
当然その後のアクションも変わってきます。
読者を応援し、励ます動機の本であれば、読んだ読者はファンになってくれるでしょうし、
読者のことよりも、自分の自慢を動機とする本であれば、逆に悪印象を与えかねません。
その印象の違いは、その後の本の売れ行きだけでなく、
あなたのビジネスへの好影響の有無、という形でも現われてくるのですね。
なおやっかいなことに、
こうした「動機」というのは根本的なものなので、
隠そうとしても隠し切れないことが多いです。
ですので本を出そうと思ったとき、
最初にやるべきは、
「読者に貢献しよう!」
というマインドセットを定めることになります。
ここがズレてしまうと、
その後いくら企画を考えても、
結局は元の動機に引っぱられてしまい、
せっかっく本を出したメリットを、享受できないことが多いのですね。
あなたの出版動機は、いかがでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
2025/01/09初心に戻って、長く活躍しよう
こんにちは、
保護ねこ8匹と暮らす出版コンサルタント、樺木宏です。
年の初めは、気分もリフレッシュして、初心に戻りやすいものですね。
特に何冊も本を出している人は、この時期がけっこう大切だと思います。
というのも、初心を忘れてしまうと、本を出し続けるのが難しくなるから。
本を出すことに慣れれば慣れるほど、アウトプットの質が下がりがちなのです。
たとえば最初の本を出すときは、
熱も入りますし、いままでの膨大な経験の蓄積が背景にあります。
だから意識せずとも、濃い内容をサラッと書けることが多いです。
自分にとっては当たり前のことが、本になっていくのをみて、
「商業出版って、こういう感じでやるのか」
と、だんだん慣れてきます。
特に、そうやって出した本がベストセラーになったりすると、
その印象は確信になって、自分の「型」が出来てきます。
このこと自体は問題ないですし、
この時点では特にデメリットはありません。
しかし何冊か出してくると、状況は変わってきます。
だんだん新鮮さも薄れてきますし、
同じ内容を何度も書くわけにはいきませんので、
新たなテーマや切り口が必要になってきます。
要するに、意欲は右肩下がりなのに逆にハードルは上がっていくのですね。
その時、先の「型」が邪魔をします。
つい、今の感覚で「この程度でいいだろう」となりがちなのです。
すでに書いたことは書けないので、そのつもりはなくとも、内容は「薄く」なります。
また著者の熱意が薄れたことは、行間から読み手にも伝わります。
だから類書と代わり映えがしない、どこかで見たような本になりがちなのですね。
こうしたことは見る人が見れば分かるので、
出版社含め、あまり本気で肩入れしなくなり、
本も売れ行きが先細り、やがてフェードアウト・・・
こうならないためにも、
新年のこの時期、ぜひ初心を取り戻して行きましょう。
最初に出した自分の本を読むのもよいですし、
最初につくった出版企画書を眺めてみるのもよいでしょう。
今後のさらなる活躍のための、ご参考になれば幸いです。



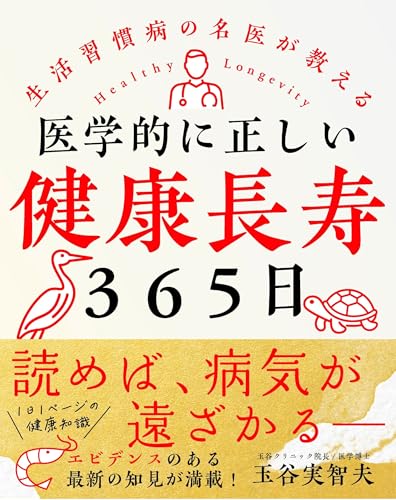
 読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
読むだけで、あなたの知識・経験が「売れるコンテンツ」に変わります。1年で30人もの著者デビューを支援しているノウハウをお伝えします。
